▷THEATRE for ALL 公式サイト / SIDE CORE「MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020」(公開は6月23日〜)
暮らす、働く、散歩する、買い物する、交流する、発信する、作り出す、破壊する…。365日何かが生み出されたり、壊されたりしながら、さまざまな人・もの・情報が入れ替わり立ち替わり、“生きている”ように新陳代謝をしている街、東京。一見、以前と変わらぬ平穏な空気が流れているかのように見える街は今、移動や行動が制限され、経済的にも、社会的にも、国際的にも一つの答えがないさまざまな問題に直面している。この難しい局面で、息苦しささえ感じる都市・東京はどこに向かうのか。そして私たちと都市の関わりはどのように変化していくのか。
コロナ禍で外出困難となった人や、障がいや疾患、育児や介護などを理由に劇場や展示などの芸術鑑賞から遠ざかる人たちに対して、誰もが好きなとき、好きな場所から文化に親しめる場の実現を目指した日本初のアクセシビリティに特化したオンライン型劇場「THEATRE for ALL(以下、TfA)」。配信中の作品のなかに、アートコレクティブ「SIDE CORE(サイドコア)」が夜の街を歩きながら、ストリートアートにフォーカスし、表層に現れない東京を解説して行く『MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020』(アクセシビリティ:バリアフリー日本語字幕、英語・中国語字幕付き)がある。今回、NEUT MagazineはアーティストでありSIDE COREのディレクター・松下徹(まつした とおる)、そして映像のなかで作品がフィーチャーされ、以前から松下とともに都市を観察批評する視点で活動してきたストリートアーティストBIEN(びえん)と、都市から読み取れるこれからの東京について考えていく。

時間のコラージュから街の価値を再定義する
深夜。15分で歩ける距離を3時間かけて。外苑前のワタリウム美術館、外苑西通り、青山キラー通り商店街から竹下通りを抜けて明治通り、渋谷のセンター街まで。「地面師に注意してください」の看板や、今はなき地名「原宿一丁目町会」の表札。コンクリートがクラックで崩れたところにあるドローイングの作品。「風景にノイズを起こす」ことを掲げ、都市や地域でのリサーチをベースに作品制作を行う松下徹、高須咲恵(たかす さきえ)、西広太志(にしひろ たいし)によるアーティストユニット・SIDE COREの映像作品『MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020』では、コロナ禍の年末、ほとんど無人に近いひっそりとした夜の街中で、現在進行形で進んでいるものから、時を留めた形跡まで、さまざまなタイムラインが並行している都市の様子が記録される。本映像を通じて、彼らが記録しようとしたこと、そして新たに見えてきたこととは何なのだろうか。

ー街を観察者の視点で捉えながら、ストリートアートと現代美術の間を繋ぐような活動をするお二人にとって、表現のキャンバスでもある街・東京の現状をどうお考えですか。『MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020』を通じて見えてきたことも含めて教えてください。
松下:街を捉えるといってもいろいろな見方がありますが、今は集まることもできない、面白いことが起きづらい、都市で生きていくことの意味自体変わっていく“間の時間”。そんな変化の過渡期だからこそ、時間や歴史という観点から都市の文脈をひもといて、街を再解釈・再定義する、ドキュメントを構築していくことが必要なのではないかと考えています。大きな流れでいえば東日本大震災以後、2011年から現在に至るまで人が集まる場所、コミュニティが必要だという思想が高まり、その概念自体がマーケティングや再開発に利用されてきた。だから人が集まることができなくなった今、ある意味街の中で何をしていいか分からない状況が生まれているとも言えますよね。ストリートでも、今までは街のど真ん中でいろいろなことが起きてきましたが、それも変化して行くのだと思います。ところで今回BIENが発表してくれた作品も、時間のクレパス、つまり街の変化のなかで置き去りになった場所にアプローチする内容でしたが、作品の内容について話してもらっていいですか?。
BIEN:そうですね。ひび割れだったりとか、壁紙が剥がれて偶然できた形だったりとか。何かが欠けているとか、きれいなものから外れているものが面白いし、それが何かの形に見えたりすることってよくあるじゃないですか。街を歩くときも、気配を感じて見てみたら何かがめくれた跡だったりとか壁が落ちた跡だったりして。それとは別で博物館に石器時代や何千年も前に使われた石のカケラを、大部分を勝手に補完して展示しているような状況が面白いなと。街にあるカケラはなんでもないものとして扱われるけど、博物館にあるカケラと同じものとして捉えて遊ぶことはできる。それが今の作品にも繋がっているんだと思います。なんでこれを作ったんだろう、なんで壊れているんだろう、なんでこういう状態になっているんだろうってちょっと前の時間を想像する。
松下:歴史もいろいろな遡り方ができますが、東京では大空襲があったので、戦後の東京の都市設計って無からスタートしているんですよね。他の人たちが疎開している間に東京にいる人たちが戦後その場所で商売を始めたりとか。街の中である意味そういった第二次世界大戦後の復興の痕跡みたいなものが残っている場所に限って、ルール設計がもともと曖昧なところからスタートしているから今でも曖昧だったりする。個人的にはそういう都市の曖昧な部分が日本のストリートカルチャーの土壌であったのかなと思います。『MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020』の渋谷のシーンで重要だったのが、昔の宮下公園から現在の宮下公園への時間のクレパスが露呈していたところ。例えば昔の宮下公園の1Fが駐車場だったころの看板がまだ残っていて「P」って書いてあるんですけど、今はない。みんなそこにステッカーを貼ってますね。昔の歩道橋と現在の歩道橋も混在しているんですが、間にスポンジみたいなものがあって手すりもグネグネグネっとしている。明かに時間の接続がうまくいっていない。LOUIS VUITTONの店舗前に「野地連」の毛布入れがあるのもおそらく世界で日本だけなんですよね。LOUIS VUITTONを誘致する場所で普通は起こらないことが起きていますよね。あれは宮下公園に野宿者がいたときの名残みたいなものがそのまま残っていて、時間のギャップ、制度設計の失敗みたいなものが分かりやすく浮き彫りになっている。

カケラが問いかける“考えさせる言語”の可能性
ー映像作品中、制度設計の失敗と思しき場所や、曖昧な要素など、普段は意識しなければ気がつかないうえに、説明が難しい「分からない」要素が多く登場します。BIENさんの作品でも、具体的なモチーフではなく抽象化されたライン(線)を用いた表現が多いと思うのですが、「分からなさ」についてお二人が考えていることがあれば教えてください。
松下:例えば落書きが多く消されない場所というのは、さまざまな原因で管理が行き届いていない場所だと思います。配電盤って(落書きが)消されないじゃないですか。あれはあえて消してしていない(一時的に落書きを残している)のだと思いますよね。。ポストとかに描くと、すごく問題になるんですよ。あとは標識に貼っちゃダメだけど、標識の裏は問題になりづらいですね。グラフィティは都市設計のなかでデザインされなかった部分をマーキングしていくというか、街の中のある種カオスな部分を表面化、視覚化しています。一方で、SIDE COREを始めた当初は、まだ今ほどストリートカルチャーが理解されていなかったし、美術に接続されて考えられてませんでしたが、2010年代以降、マーケティングや都市計画にストリートカルチャーが使われるようになってきた。ある意味どんなエッジーなことも単純化されて資本に回収されてしまう、カルチャーにとっても非常に難しい時代だと感じます。だから僕たちの今の役割としては街に関する作品を作ることで街の中のある種カオスな部分、理解されにくい分かりにくさを表面化、視覚化していくこと。表現することを通じて都市を身体化させていくこと、内在化させていくことだと思うんですよね。『MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020』はだからこそバラバラの文脈を持つ物事を同時に扱ったり、即興的な表現を展開したり、街を単純化して考えないことを重視しています。

BIEN:今まで見ていたもの、こうだと思っていたものが実はそんなにガッチリと固まったものではなくてとても不安定なもので、ただ自分がそう思い込んでいるだけだったり、教育に影響されてそう認識していただけだったりすることがありますよね。作品を作ることでそういったことに気がつけたら面白いなと思っています。一枚の絵を描いたときも、一枚で終わりではないというものを作りたいんですよね。欠けている部分を埋めるという方法も、ない部分を想像する作業で、自分でも知らなかった見え方が発見できたりする。例えば自分のなかでは文字には見えかったものがそれ文字だったんだ!とか。実はひらがなと漢字と中国語とタイ語とか見たときにも同じことが起こっていて、僕らには読めなくても、読める人にとっては普通。分からなさは必要なものだと思うので、それはあえて分からないところを作るようにしているしうやむやにしています。
松下:BIENの作品に関していえば、鑑賞者に委ねられている部分が面白いと思います。モチーフがあるようでないようないい塩梅で抽象と具象の境界線にドローイングを展開している。偶然かもしれないけど恣意的かもしれない、その思考の中間の表現が面白いと思っています。

一人一人が都市を「見る」方法を見つけることで新たな文化がつくられる
ー変化の渦中にありながら、今もなお人と集まって話したり、行動を起こしたりすることが難しい状況が続いている街で、今私たちにできることは何だと思いますか?これからの都市での生活を見据えて、時代のコラージュを読み解いたり、街を「見る」方法についても教えてください。
松下:街の中でアクションを起こすという視点においてやっぱり今東京って難しいなと思います。街の中のルール設計がすごく強固ですよね。相互監視の力も強いし、不確定要素は排除されていく。地価が高騰しているし不動産は高いので、場所自体へのアプローチは難しいと思うんですよ。でも、「時間」というレイヤーや街を見てみるといいのかもしれない。都市の中で何かをするのであれば時間を区切れば自由に使える瞬間ってあるんですよね。例えば夜オフィスが閉まっているのであればオフィスで何かできるわけじゃないですか。場所ではなく時間で都市を見ると何か表現の可能性ができるかも。イベントを開く場所を手に入れることができなくても、イベントを時間のなかで作ることはできるから。当たり前っちゃ当たり前なんだけど、普段場所を占拠しないとできないことを、時間のなかで行うみたいなことはできるんじゃないですかね。
BIEN:以前ヨーロッパを一人で旅したときに、バスの窓から撮った写真だけでZINEを作ったんです。街中で、ただ歩いているだけだと気に留めなくても、いろいろ“見方”は自分で設定できると思うんですよ。ポスターだけとか、消火器だけとか。なんでもいいから一つでも気になるものがあったら、他にも見つけてみようと集中して見てみる。ある意味何も写っていない風景写真なんだけど、ルール設計して集めていくことでそこに視点が生まれるわけじゃないですか。そういう作業を作家として普段からやっているんですよね。そこからストーリーが勝手にできることもあるし、作ることもできる。自分も去年一年はずっと東京にいて、キツイなと思ったときに山に足を運んだりして都市と自然を分けて考えていたんです。でも一年経ってみて、そこの差を作らなくていいなと思いました。都会も、コンクリートやビルの溢れている“都会”という名前のついている“自然”。あまり差をつけないで見られないかなと。なので個人的にはこれからもっとフィールドワークを増やしていきたいと思っています。今ではどこに行っても面白いと感じますね。
松下:要するに散歩なんですよね。目的地に対して移動していくことは設計されたなかを水平に移動していることになるけど、いつもの場所でも視点を変えて見てみれば有機的な体験を生み出すことができる。それは東京だけではなく、どこでも持つことのできる視点です。今している話、都市の文脈を読み解くことは「今」だから必要なことだと思っていて。都市が前進しているときは必要ないと思うんです。でも今、都市がいろいろな意味で停滞している時期だからこそ、もう一度自分はどういうものが好きなのか、成り立ちを読み解いたり、なんでそれが面白いと思うかを考えると批評的観点を持つことにも繋がります。そうすることで何を消費したいのか、どういうふうに生きたいのか、自分の趣向も分かってくる。今はなくなってしまったものや場所であっても、調べてみて、実際にその場所に行ってみても面白いと思います。見えないものを想像する力によって、文化って担保されていくのではないかなと思いますね。
今、「東京」と言われて思い浮かべるのは、どんな姿だろうか。ぼんやりとおぼろげなシーンが浮かぶ人もいるかもしれないし、特定の時間と場所が浮かぶ人もいるかもしれない。それはおそらく私たち一人一人がこの街で過ごしてきた時間の軌跡であり、未来に向かって想像するまだ見ぬ都市の姿なのではないだろうか。暮らす場所でもあり、働く場所でもあり、訪れる場所でもあり、訪れたことのない場所でもあるかもしれない、
一人一人にとって異なる表情を見せる都市・東京。1300万人の人が住み、目には見えないルールや多くの問題に直面する都市の未来は、まだ誰にも分からない。けれど複雑に絡み合い、今までに紡がれてきた東京に存在する時間のコラージュを読み解くこと、そして今現在も進行している都市の変化を、しっかりと記憶に留めること、つまり一人一人が観察する視点を持つことが各々の未来の都市を形作っていくのかもしれない。

松下徹 Tohru Matsushtia
アーティスト/SIDE COREディレクター
1984年神奈川県生まれ、東京藝術大学先端芸術専攻修了。化学実験や工業生産の技術によって絵画作品を制作。高電圧の電流によるドローイング、塗料の科学変化を用いたペインティングなど、システムが生み出す図柄を観測・操作・編集するプロセスにより絵画作品を制作。またストリートカルチャーに関する企画を行うアートチームSIDE COREのディレクターの1人でもあり、国内外のストリートカルチャーに関するリサーチ/執筆をおこなっている。
展示歴
2021 「水の波紋」ワタリウム美術館 東京
2020 「Long Circuit」HARUKAITO by island 東京
2019 「Cutter」 SNOW CONTEMPORARY 東京
2019 「Reborn-Art Festival 2019」石巻市 東京
2019 「un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング」戸田建設 東京

BIEN
1993年東京都生まれ、ドローイング表現を基礎とし絵画や彫刻など多様なメディアで作品を制作。アニメのキャラクターなどフィクションが生み出す形、文字や記号などの表象に着目し、それらがもつ形や意味を解体/再構築する抽象表現を展開している。またロックミュージックやストリートカルチャーなど、多様なサブカルチャーに精通しており、多様な文脈をミックスしたアプローチもBIENの表現の特徴である。 主な個展に、18年「WOOZY WIZARD」(BLOCKHOUSE、東京)21年「DUSKDAWNDUST」(PARCEL、HARUKAITO by island、東京)など。
▷Instagram

作品の視聴はこちらから
SIDE CORE「MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020」
配信期間:2021年6月23日(水)〜8月23日(月)
視聴料金:¥1000(視聴可能期間は購入から10日間)
上映時間:88分
アクセシビリティ:バリアフリー日本語字幕、多言語字幕(英語・中国語)
視聴:https://theatreforall.net/movie/nightwalk/
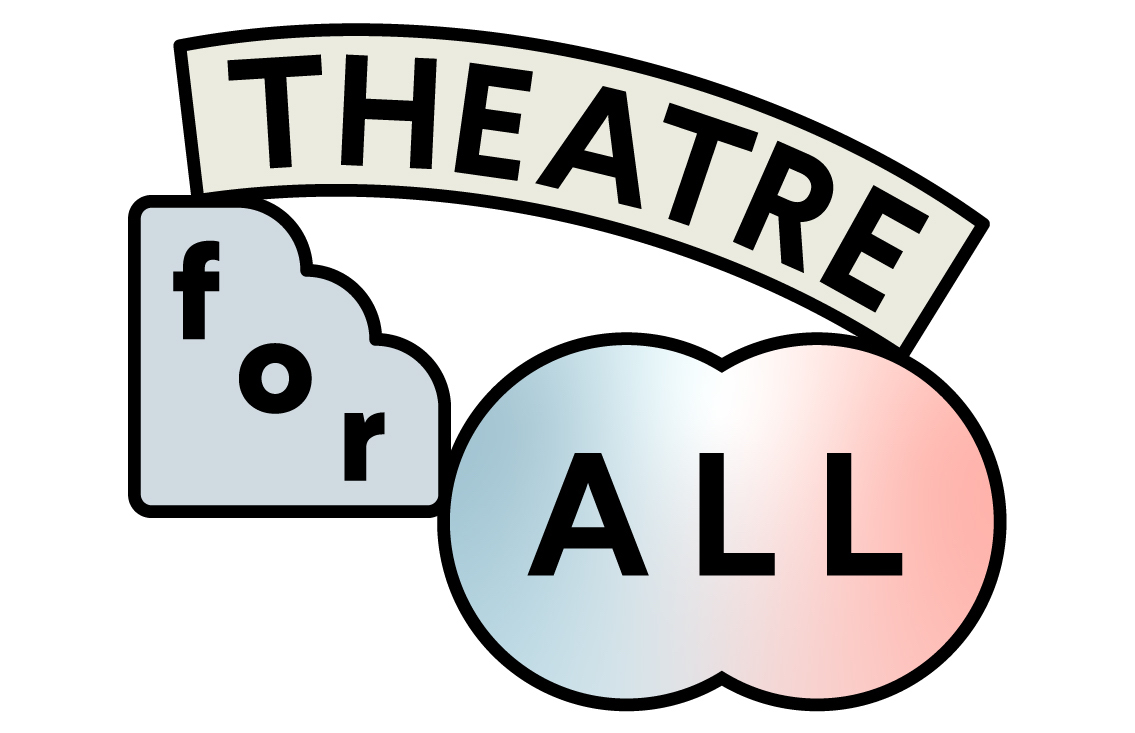
THEATRE for ALL
株式会社precogがオープンした、日本で初めて演劇・ダンス・映画・現代アートを対象に、日本語字幕、音声ガイド、手話通訳、多言語対応などのバリアフリー対応を施したオンライン型劇場です。 現在、映像作品約30作品とラーニングプログラム約30本を配信。さまざまなアクセシビリティに対してリサーチ活動を行う「THEATRE for ALL LAB」の活動も行っており、障がい当事者やその他さまざまな立場の視聴者、支援団体などと研究を重ねています。また、作品の配信に加え、鑑賞者の鑑賞体験をより豊かにし、日常にインスピレーションを与えるラーニングプログラムの開発に力を入れています。
▷THEATRE for ALL 公式サイト

















