8月11日、土曜日。東京生まれ、無農薬育ちの有機野菜を作る「Ome Farm(以下、青梅ファーム)」と、ほかにないデザインでファッション業界の一角に位置する「minä perhonen(以下、ミナ ペルホネン)」が共同で、親子向けに野菜をテーマにしたワークショップを開催した。
イベントの会場になった、ミナ ペルホネンが提案する心地よい暮らしのアイテムを揃えた「call(コール)」のテラスに、ミナ ペルホネンを愛用する親御さんに連れられた子どもたちが、「一体ここで何が始まるんだっけ?」という面持ちで現れては席に着いていく。
そんな子どもたちの前に立ったのが、青梅ファームの代表である太田太(おおた ふとし)さんと、同じく青梅ファームの種のスペシャリストである島田雅也(しまだ まさや)さん。


ワークショップは、種のスペシャリストである島田さんが、いつも目にする野菜はどのようにして育っているのか、米粒のような小さな種にどれほどの生命力が凝縮されているのかなど、学校では学べない特別授業を開講し、その後太田さんが、青梅ファームの野菜を使ってのサラダ作りを子どもたちにレクチャーするという流れで行われた。
ちなみにこの日会場には、ミナ ペルホネンの創業者でありデザイナーを務める皆川明(みながわ あきら)さんも駆けつけた。

さて、ファッションの分野に身を置くミナ ペルホネンが、なぜ農家である青梅ファームとタッグを組んでこのイベントを開いたのか。そのあたりの思うところも皆川さんに聞きつつ、駆け足気味ではあるが、イベントのレポートを掲載する。
消えゆく自家採種と種の話
青梅ファームと自身の自己紹介を終え、農業に欠かせないミツバチの働きや、野菜の種の基本要素を説明し、授業がひと段落した段階で島田さんが言った言葉に、子どもたちが「それってやったことないかも」という顔をした問いがある。
それが、「皆さんは野菜の種を採取したことがありますか?」というものだ。

畑やプランターで、固定種*1と呼ばれる種から野菜を自家栽培して自家採種している、もしくはそれをしていたという人。そういった方々には馴染みがあるであろう、種から野菜を育てて採取して、また種から育てるというサイクル。
自家栽培はともかく自家採種は、今となってはあまり見られなくなった光景の一つだ。
その背景には、戦後混乱期において食生活を安定させるために、自家採取には適さないが、さまざまなニーズに合わせて改良を加えられたF1種*2が勃興したという事情がある。増え続ける人口に合わせて、安定した食料供給には適さない固定種野菜は姿を消していった。
また、固定種野菜の衰退にともなって、自家採種を行う農家も急減し、現在に至る。
(*1)固定種(こていしゅ)。それぞれ土地で長期間にわたって育てられ、自家採種を繰り返すことによって、その土地の環境に適した遺伝的要素を蓄積し、安定していった品種の総称。味やサイズに個体差があり、個性のある野菜として親しまれてきた。しかし種から実るまでの過程にも個体差があり、ゆえに安定した食料供給の仕組みには組み込みづらい。
(*2)F1種(えふわんしゅ)。異なる性質を持った種を人工的に掛け合わせて、さまざまなニーズ(形を均一にする、特定の病気に強いなど)に応じて作ることができる雑種。別名で一代雑種(いちだいざっしゅ)とも呼ばれるため、採取できないとの誤認も多々見受けられるが、その生産方法(二代目には一代目とは正反対の性質が受け継がれる)の仕組み上採取に適さないだけで、採取自体は可能である。
種の未来は小さな一歩から。自家採種のススメ

そんな自家採種を「ぜひやってみてください!」と呼びかける島田さん。それには、絶滅の危機に瀕している固定種野菜の存続を願う気持ちと、子どもたちの未来に種の多様性を確保したいと願う一人の親としての思いが合わさっていた。
「固定種がいいもので、F1種が悪いものなんて僕はまったく思いません。ただただ、子どもたちの未来に種の選択肢を残してあげたいだけなんです」。

そんな島田さんの授業は、自家採種という失われつつある慣習に触れて終了。この授業を受けて、参加者の親子が一緒に自家採取をやってみるということは起こりうるだろうか。「種の未来は、こういう小さな一歩で変わるんじゃないかな」。そう島田さんは言う。
続いて太田さんによる、「これを機に家事のお手伝いをしてあげようね」というサラダ作りの実践講座がスタート。

子どもたちは太田さんが教える手順を真似て、手で野菜をちぎり、水を切る特大の野菜スピナーを懸命に回し、オリーブオイルとワインビネガーで味付け、と順次工程をこなしていく。
実際に食べる段になると、「酸っぱい!」や「おいしい!」など、いろんな声が聞こえてきて、机の上は賑やかなムードに包まれた。


そんな明るい喧噪の隣で、ミナ ペルホネンの皆川さんに、今回のワークショップを開いた経緯と、ファッションブランドが食に携わる理由を聞いた。
「生活は切り離せないし、そもそも切り離すべきではありません」
今回ミナ ペルホネンが「call」で、青梅ファームとともに、野菜をテーマにワークショップを行ったのはなぜか。

その心を聞くと、皆川さんは、「ファッション、インテリア、建築などのデザインは、それぞれカテゴライズされて、切り離されてきたと思います。しかし実際、生活空間のどこにもそれらは同時にあって、同時に使っている。だから切り離せないし、そもそも切り離すべきではありませんよね」と言い、こう続けた。
もちろん僕たちは、テキスタイルやファッションを中心にもの作りをしてきました。でも、そのときの目線は、インテリア、建築、空間、食に関わったときにも通ずるものだと実感しています。さまざまなものを同じ目線で見る、ということですね。だから、東京出身のおいしい野菜を扱う青梅ファームを、こういう形で紹介できるのは嬉しいなあと思います。ほかにもここ「call」では、ワインのイベントをやったことがありますし、ファッション業界以外の方々とのコラボレーションをたびたび行っています。

創業から数年とまだ間もない頃に、独自の家具のデザインや、ファッションブランドでありながらインテリアファブリックの販売を始めた。また、オリジナルファブリックから始まる服づくりの背景を伝える個展『粒子ーーparticle of minä perhonen』を開いたこともあるミナ ペルホネン。その歴史から鑑みても、分野を横断する試みの数々は、皆川さんにとっては自然な思考の先にある、自然な選択だったのだろう。
周囲の皆様からは、確固たるスタイルがミナ ペルホネンにはあるとおっしゃっていただけることもありますが、まだまだ改善点があると僕たちは感じています。トライアルの隙間はいつもあるんです。だから僕たちは、こんな食材や、こんな服や、こんな素材があるよということを、分野を問わず発信していく。それをお客様にご判断いただき、選んでいただければいいかなと思っています。
“100年続くブランド”を標榜するミナ ペルホネンと、“本当に安心できるものを都心近郊でつくる”ことを目標に掲げる青梅ファーム。どちらのブランドも、ものを作るという共通点があるのだが、それ以上に、「自分たちが作りたいものを作っている」というある種のプライドが見受けられる。


「作り手が楽しんでいなければ、どんなに『サステイナビリティ』という言葉が世の中に普及しても、本当の循環が生まれることはないんじゃないかなあと考えています」という皆川さんの言葉は示唆に富む。
分野を問わず、ものを作り提案するあらゆるブランドは、ときに自分たち本位で物作りを考えるという、一種のわがままさを持っていてもいいのかもしれない。
Akira Minagawa(皆川 明)
1967年東京生まれ。1995年に自身のファッションブランド「minä(2003年よりminä perhonen)」を設立。時の経過により色あせることのないデザインを目指し、想像を込めたオリジナルデザインの生地による服作りを進めながら、インテリアファブリックや家具、陶磁器など暮らしに寄り添うデザインへと活動を広げている。また、デンマークKvadrat、スウェーデンKLIPPANなどのテキスタイルブランドへのデザイン提供や、新聞や雑誌の挿画なども手掛ける。

minä perhonen(ミナ ペルホネン)
オリジナルの図案によるファブリックを作るところから服作りを進める。国内外の生地産地と連携し、素材開発や技術開発にも精力的に取り組む。ブランド名は、デザイナーがスカンジナビアへの旅を重ねる中で、そのライフスタイルやカルチャーに共鳴するというフィンランドの言葉から取った。「minä」は「私」、「perhonen」は「ちょうちょ」を意味する言葉。蝶の美しい羽のような図案を軽やかに作っていきたいという願いを込めている。ブランドロゴは、「私(四角)の中のさまざまな個性(粒の集合)」を表す。蝶の種類が数え切れないほどあるように、デザイナーの生み出すデザインもまた、増え続ける。

call(コール)
聞こえますか?
今は世界のどこかに在る
ものたち
海の向こうから
日々の手の中から
遠い記憶の中から
たった今の想いから
生まれてきたものたちを
呼びよせて
そこに息づく物語に
耳を澄ませて
暮らしの中で
寄り添ってみる
「callより」
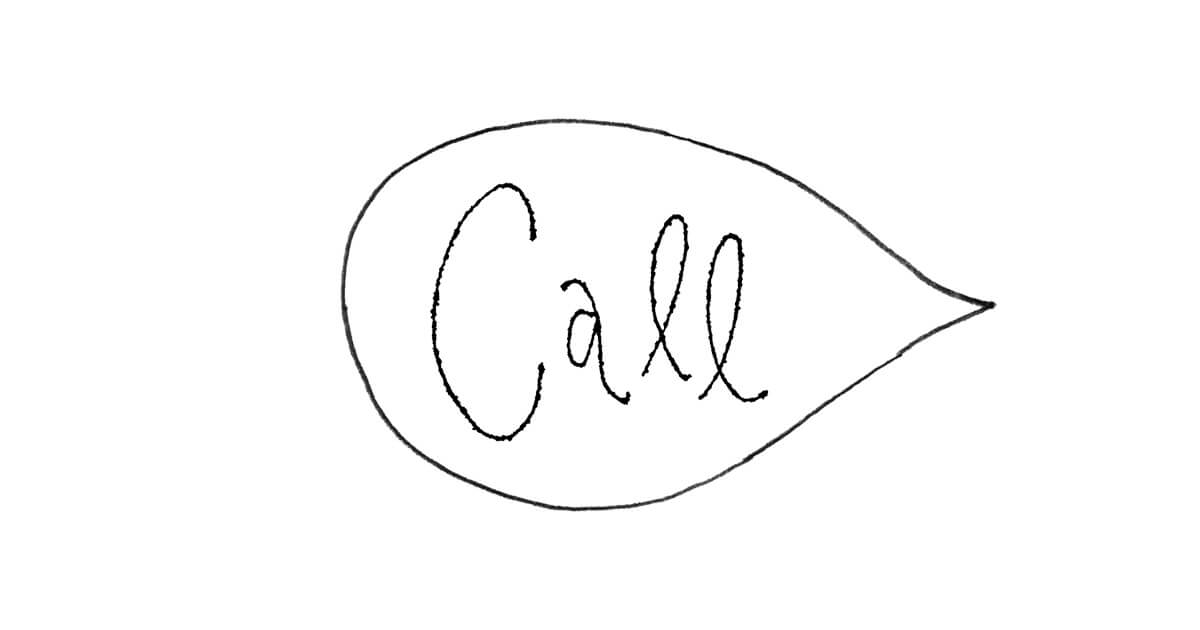
※こちらはBe inspired!に掲載された記事です。2018年10月1日にBe inspired!はリニューアルし、NEUTになりました。

















