SNSの台頭やストリーミングの普及により、日々変わりゆく音楽業界。「歌がうまい」「作詞の才能がある」「演奏がかっこいい」、それだけの理由だけでなく、誰もがアーティストになれる時代となった。多様性が重視され、さまざまな考えが溢れるこの現代社会で、ただ音楽を伝えていくだけではなく、アーティストの価値観や主張を紐解き、発信していくことの必要性について、一度考えてみたい。

音楽業界で主に海外アーティストのマーケティングとして、Rina Sawayamaやコナン・グレイなどの担当をしてきた笠原力(かさはら ちから)と、アメリカを拠点に、アーティストのPRやコンサル、音楽ライターとして活躍し、2022年に『世界と私のAtоZ』を執筆した竹田ダニエルは、昨今の流れを見て「今までの音楽業界が持つ常識を崩していき、世に新しい価値観を与えていくことが必要になってくる。その突破口が洋楽にあるかもしれない」と、話す。今回は、そんな音楽業界が抱えるあらゆる事柄をピックアップしながら、今後アーティストや音楽業界はどうなっていくべきかを語ってもらった。
Instagram / Twitter
1997年生まれ、イギリス出身。アメリカ・カリフォルニア州で幼少期を過ごし、日本に移住。学生時代にiFLYERで海外アーティストのインタビューなどを行い、2019年からユニバーサルミュージックの洋楽レーベルにてインターンを開始。翌年からアーティスト担当となる。担当アーティスト: コナン・グレイ、リナ・サワヤマ、オーロラ、カーリー・レイ・ジェプセン、ジョナス・ブルー、グリフィン、ジュース・ワールド、ルイス・キャパルディ、トロイ・シヴァン、イヤーズ&イヤーズなど。現在は広告代理店でマーケティングを担当。
竹田ダニエル
Website / Twitter / Instagram
1997年生まれ、カリフォルニア州出身、在住。そのリアルな発言と視点が注目され、あらゆるメディアに抜擢されているZ世代の新星ライター。「カルチャー ×アイデンティティ×社会」をテーマに執筆。「音楽と社会」を結びつける活動を行い、日本と海外のアーティストを繋げるエージェントとしても活躍。近刊に、文芸誌「群像」での連載中からSNSを中心に大きな話題を呼んだ『世界と私のA to Z』(講談社)
アーティストは、神様でもなく、商品でもなく、同じ人間だ
ユニバーサルミュージックでRina Sawayamaやコナン・グレイの担当として、海外アーティストのマーケティングを担当していた笠原力と、SIRUPなどのアーティストのPRやコンサル、音楽ライターとして活躍する竹田ダニエル。それぞれ違う目線からアーティストに接するうえで大事にしていることや、必要なことを話してもらった。
ーまず、二人が出会ったきっかけを教えてください
竹田ダニエル(以下、竹田):今から3年ほど前、「Forbes Japan」の「30 under 30」で、企画内のコラム執筆を頼まれたことがあって、取材者の候補者に、当時笠原が担当をしていたアーティスト、コナン・グレイをあげていました。そこで彼を紹介してもらい、コナンのインタビューをセッティングしてもらったのが初めての出会いです。
笠原力(以下、笠原):そのやり取りがきっかけで、コナンが2021年にリリースしたシングル「Overdrive」のPR周りを手伝ってもらったり、2022年にリリースした2ndアルバム「Superache」のライナーノーツ(解説や歌詞が記載された紙、冊子)を書いてもらったり。いろんなお仕事をご一緒するようになりました。どれも印象に残っていますが、なかでも私が担当しているYears & Yearsのオリーが、ソロ・プロジェクトを発表するタイミングでリリースした「Starstruck」を、ダニエルがコンサルを担当しているSIRUPとコラボレーションで作品を発表したのがいい取り組みだったなと思います。それぞれ、イギリス・日本・アメリカが拠点なので、時差でなかなか打ち合わせができる時間が少ないながらも、それぞれのアーティストの新たな部分を引き出して、世に産み落とすぞという気概でできた作品になりました。
※動画が見られない方はこちら
竹田:海外アーティストと日本のアーティストのコラボでよくある話が、それぞれが一度も話したこともないまま、作品が世に出てしまうこと。著名人同士がコラボレーションしたら、もちろん数字や、エンゲージメント的にはいいのかもしれないけど、自分たちが作品を世に出すなら、きちんと互いがリスペクトし合うことがベースとしてあるなかで、曲を作ることが重要だと思っていました。SIRUPはデビューする前から、大阪のカフェやライブハウスでYears & Yearsのカバーを披露していましたし、オリーもSIRUPが過去にコラボしていたJoe Hertzの曲を聞いていました。それぞれが本当に距離の近い形で関係性を築くことができたからこそ生まれたものだなと思います。
ーアーティストのベストな状態を引き出したり、より良い関係性を築いていくために大切にしていることはありますか?
竹田:アーティストは、普段から知らない人に囲まれて仕事をすることがほとんどなので、もちろんコミュニケーション能力が高い人が多いけど、常に自分を開示し続けることは、普通に人間として大変なこと。たくさんの関係者に囲まれ、自分が「搾取されている」と感じてしまい、閉じこもってしまうアーティストも少なくありません。けど、笠原が担当しているシグリットや、Rina Sawayamaへの接し方を現場で見て、アーティストだから神という目線でもなく、商品という見え方でもなく、きちんと人として接しているのがすごくいいなと思いました。日本のアーティストでもやっぱりチームによってカラーが全然違っていて、あらゆるフェスやライブを見てきたけど、現場の仕事って改めて大事だなと感じました。バンドのメンバーはもちろん、マネージャーやレーベルの人の人間性って、ファン層にも響いてくると感じていて、見えないところでのアーティストとのコミュニケーションや環境づくりって、本当に重要なんですよね。
笠原:アーティストも人間だし、いろいろな大人たちと仕事を通して関わってるから、人をすごい見ているところがあるんです。それぞれでやり方はあると思うけど、私の価値観的に、本当にいいものが生まれるときって、それぞれのハートとハートが向き合ったときだと思うんです。だからこそ、芯食った会話や、接し方をすると、「この人とはもっと踏み込んだ会話してみよう」「普通はうーんって思うけど、この人が言うなら挑戦してみよう」とか、より一歩踏み込んだリアルな部分に繋がると思っていて、何気ない普段のコミュニケーションが、アーティスト全体に関わってくるすごく大切な要素だと思っています。
竹田:インタビュアーとしての目線からだと、まずはその人がどういう人間なのかということを大切にしていて、どうやって接するべきかもすごく考えます。インタビューを始める前に、どういう質問が好きか嫌いか、セクシャリティはどうなのかを確認するようにしています。アーティストと接するためのガイドラインやルールがない無法地帯だからこそ、難しい部分もあるけど。
笠原:ルールがないからこそ、その人として、アーティストの人間としての魅力や信念みたいなものをベースにこちらは動いていかないといけないなと思います。
竹田:あと日本だと、基本的に音楽のことはサウンドでの切り口の記事がすごい多いなと思っていて、言葉の壁もあるし、まだ多様なアイデンティティの価値観が浸透していないからだと思うんですが、海外だとポップシーンにいけば行くほど、インタビューやレビューでもアーティストの人としてのあり方を尊重する傾向にあります。SNSが浸透するまでは、ニュースや新聞など統制された情報しかなかったけど、今ではアーティスト本人がどう見られたいかというのも割とコンロトールできるような時代だし、SNSで人間的なリアルな部分が見えてくるようになって、買い物は投票と同じような温度感で、アーティストを一人の人間として尊重できるかもすごく大切な部分になってきてると思います。この人の倫理観には同意したくないから、聞きたくないとか、この人の考えに共感できるから聞くとか。日本だと、アーティストは政治や価値観の話をしないけど、海外だと、その部分がアーティストとしての責務だと思っている人は多いですよね。
音楽と出会い、アーティストのメッセージから自身の世界が広がっていく

学生時代に洋楽を聞き始めたという笠原と竹田。それぞれどんな音楽と出会い、どういった経験をしてきたのか。楽曲の素晴らしさはもちろんのこと、二人が音楽を通して感じてきたものは、アーティストが音に乗せて伝えてくれたメッセージだった。
ー笠原さんが音楽業界を志すようになったのはどうしてですか?
笠原:学生時代にレディー・ガガの音楽に出会ったことが一番大きなきっかけです。自分が思春期で結構センシティブなときに、彼女が打ち出す「自己愛」のメッセージに共感して、いつかこんなすごい人と仕事をしてみたいなという気持ちが芽生えました。そこからどこのレーベルの所属なのかを検索したら、ユニバーサルミュージックだったんです。ここに入社したら、いつかガガと仕事ができるかもと思ってずっと入りたいなと思っていて、昔ファンを集めて意見を取り入れるアンバサダープログラムに参加した際に知り合った恩師で大先輩の方にインターンシップに誘っていただいたんです。そこからユニバーサルで働き始めました。実際、間接的にですが、ガガの仕事を手伝う機会にも恵まれて、本当に光栄でした。
竹田:ガガに出会って、世界や価値観が広がったのってすごく分かる。
笠原:めちゃめちゃあるよね。デビュー当時からLGBTQ+コミュニティの代弁者ではあったけど、とくに2011年にリリースされた2ndアルバム「Born This Way」は、当時まだアメリカでもまだ今ほど同性婚について語られていないなか、彼女がメッセージとして発信してくれた。これだけの知名度があって、影響力のある人が打ち出してくれたことで、「自分は間違ってない」「このままでいいんだ」と、パフォーマンスや曲を通して教えてくれたし、学校でいじめられたりしたこともあったけど、彼女がこう生きているから、私もこうやって生きていくという気持ちになれたし、本当に助けられたんです。やっぱり、このときにアートやアーティストのメッセージで救われる感情を、自分で実際に体験しているから、私が担当していたコナン・グレイやRina Sawayamaが何かセンシティブなメッセージを伝えるとき、彼らが自分自身を赤裸々に出すことを私は尊重していて、それらを必要とする人たちに向けて、きちんと分かってもらえるように、丁寧に伝えていくことをすごく大切にしてきました。
竹田:あのときの日本でのガガの打ち出し方って、割とそのままだったイメージ。今だったら、芸人さんと絡ませたりしてネタっぽい感じにもできそうなのに、そういうパターンじゃなくてシンプルに海外のスターとして発信していたし。あと、「かわいい」とかじゃなくても、売れるっていう先行例だった気がする。
笠原:そうなんだよね。変に加工しないで「彼女はこれが素晴らしいです」と、あくまでもレディー・ガガという1人のアーティストとしての人間的な魅力を、そのままの状態で日本でも伝えてくれたからこそ、変に誤解を生まずに多くの人に受け入れられて、今も変わらずに支持され続けているんだと思う。そういう前例を見てきたからこそ、あえてイロモノ的な視線に振ってアーティストを見せていく必要はないんだなとも思った。そういう切り口で見せていくと流行り廃りもあるから、どんどん色褪せてしまうのもあるしね。
ーダニエルさんはどういった音楽的なバックグラウンドがあるんでしょうか?
竹田:子どものころピアノを習っていたのですが、ピアノも嫌いだったし、音楽も好きではありませんでした。親がピアニストになりたいという自身の夢を叶えられなかったことから、その夢を私に投影していたからだと思います。それなりに上手かったけど、やらされてる感じが拭えなくて、まったく興味を持つことができなかったんですよね。そんな感じだったんですが、幼馴染が誕生日にiPodをプレゼントしてくれたことをきっかけに、洋楽を聞くようになりました。当時のiTunseのTOP30を入れてくれていて、ワン・ダイレクションやケシャ、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフトなどがラインナップしていましたね。
笠原:懐かしい。当時はポップス全盛期だったよね。

竹田:そうそう。SNSも今ほどではなかったから、みんな同じヒットソングを聞くみたいな感じだった。私はそこから洋楽を調べるようになって、年に数回日本に旅行で来るするタイミングで、テイラーのCDを買って、ライナーノーツを読み込んだりしていました。初めてライブに行ったのも、日本がスタート地点だったテイラーの1989ツアー。そのとき、ゲストでハイムが出るという噂が流れたんです。
当時の私はポップスのヒットチャートしか聞いてなかったから、ハイムのことも知らなかったし、オルタナロックというジャンルもよく分かりませんでした。けど、もし出演するなら聞いておこうと、iTunesでハイムのアルバムを購入したんです。せっかく自分で買ったからには、元を取るために聞かなきゃと、毎日のように聞いていました。そのうちハイムのことが大好きになって、今でも大ファンです。結局、ゲストの話は噂で終わってしまうんですが、洋楽をさらに好きになる出来事でした。しかも、当時はTumblerが流行っていて、ラナ・デル・レイや、フローレンス・アンド・ザ・マシーンが、アートやファッション的な文脈でじわじわと人気を集めていたんです。その視点から好きになるアーティストも増えて、フェニックスや、キャットフィッシュ・アンド・ザ・ボトルメンなどのライブに行ったり。またそこからグッと音楽への世界観が広がっていったように思います。
ー音楽業界へ携わるようになったきっかけを教えてください。
竹田:音楽の世界観をキュレーションするセンスがあると自覚していたので、そういうことをしたいなと漠然とは思っていたのですが、根本的には自分のバイリンガルを活かせることをしたいと思っていました。逆のパターンでも言えることですが、日本のアーティストで、せっかくポテンシャルがあるのにも関わらず、インフラが整備されてないから海外での活動が難しかったりするのを、どうにかしたいなとも思っていました。そういった思いもあって、アメリカの大学のビジネススクールで、ミュージックビジネスのプログラムがあって、受講することにしたんです。そこで実際にアーティストのマネジメントする課題が出て、そこから音楽業界にコミットするようになりました。そのタイミングで、Twitterも始め出して、音楽プロデューサーのstarRoやSIRUPのコンサルやPR業務、通訳や執筆など幅広く活動するようになっていったという感じです。
音楽業界のこれまでの常識を壊すことで見えてくる新しい価値観
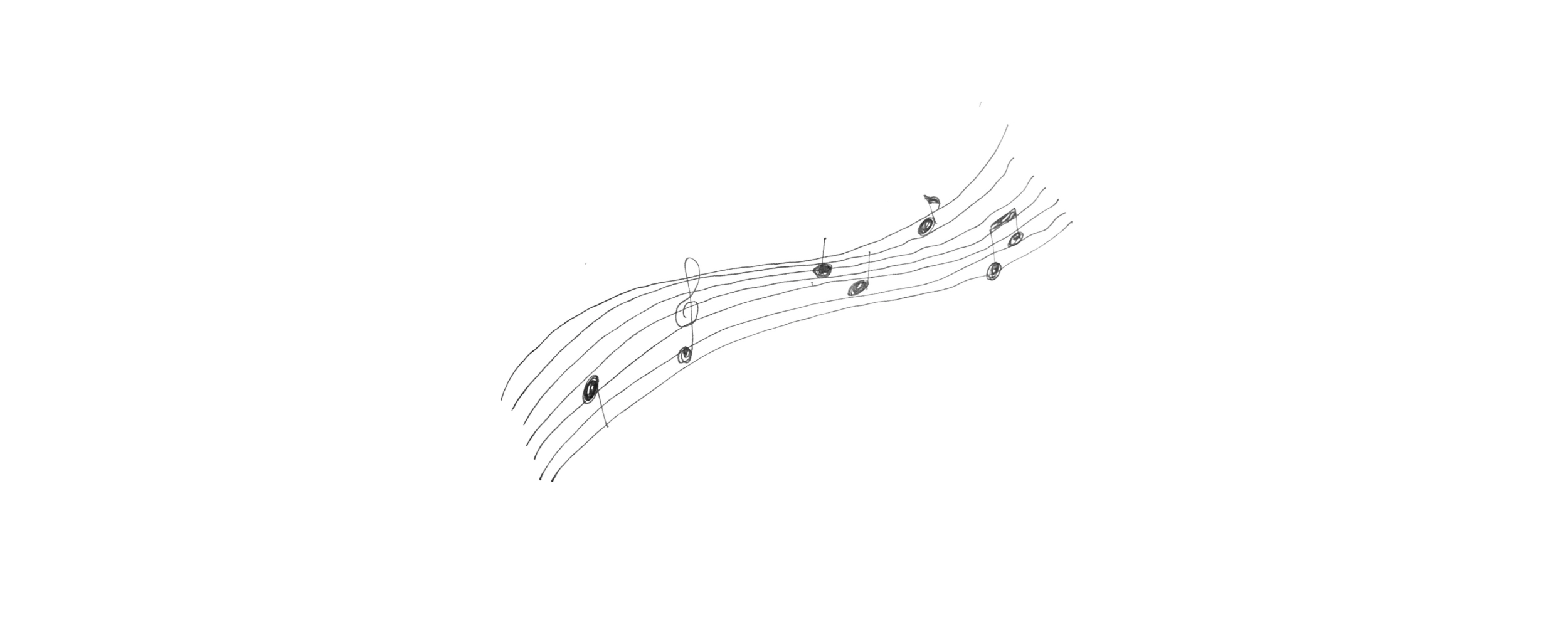
それぞれが違う立場からアーティストと仕事するうえで共通して感じているのは、見え方だけでなく、まずは本質的な部分を追及していくこと。これから音楽業界やアーティストにとって必要なものは一体どういうものだろう。業界のこれまでの常識を崩し、新しい価値観を作っていくことの大切さとは?
ー二人がそれぞれ違う立場で音楽業界に身を置いていて感じることは?
笠原:キラキラしている業界だからこそ、誰かが何かを我慢して健全ではないサイクルが続いてしまうことですかね。今ってストリーミングが普通の世の中で、誰もがアーティストになれる時代。いろいろな場所でいろいろな人が求められているのに、予算の捻出が難しくてツアーがなかなかできない状況になったりしていて、ヒットを出さないとお金がなかなか回収できないビジネスモデルになってきているなと思います。どんなにキツくても輝いてる場所だから、それすらも良しとしてしまう傾向が続いてしまっているんですよね。
竹田:コロナ禍でツアーができなくて、アメリカだと3回くらい会場が充ち満ちに埋まらないと黒字にならないみたいな地獄的な状況もほとんどの人が知らなくて、チケット会社にすごくマージンを取られてしまうことに対して、多くのアーティストがそれを嫌だと感じていたのに、ようやくテイラーが問題定義したことで、世の中にその実情が伝わったみたいな流れがありました。これまでアーティストがそういった発言をすることは割と避けられてきたんですが、アメリカではようやくそれがオープンに話せるようになってきました。要は、売れていることや、華やかな世界みたいなものにすごく執着してるけど、もうこんなご時世だし、それって意味あるのかなっていう。
笠原:こういう業界だし、実は華やかじゃなくていいんだよというのをそれぞれが受け入れて、もうちょっと持続可能で、健全な形でビジネスと向き合うことは今後もっと大切になってくると思う。多分これからもっといろいろなアーティストが増えてくるし、業界の性質的に難しいかもしれないけど、こういった状況を改めて受け入れることで、アーティスト本人や、関わっている周りの人にとってもすごくプラスの働きをすると思います。
竹田:あと最近改めて思ったのですが、見え方を気にしすぎている部分があるなと思います。例えば、日本だとツアーのチケットの宣伝をたくさんし続けたら、チケットが売れてないみたいな見え方になるとか。そういう感覚的なことや、売れてる幻想を作るのにみんな忙しくしていて、それをするくらいなら誰か一人でもツアーに行きたいと思わせるようにしたほうがいいと思うんです。なので、いわゆる業界でのこれまでの正しい常識や、今まで当たり前だと思っていたことを、問いただすのはすごく大事にしています。他にも、著作権の問題なのか、ライブでは撮影禁止のところが多いですが、インディペンデントなアーティストこそ、ライブの良さが大切になってくると思っていて、個人的にもったいないなと思っていることの一つ。全部撮影可能じゃなくとも、1曲だけ撮影OKにするとか、そういう柔軟性も必要だと感じています。これまでの常識を崩していくことで新しい価値観も生まれていくと思うんです。
笠原:アーティストもクリエイターだから、今までになかった新しいものを生み出していきたいと思っていると思うし、時代の流れや必要性に応じて、やり方をどんどん変えていくことが必要だよね。
竹田:笠原で言うと、Rina Sawayamaのサマソニのスピーチは本当に名場面だった。
笠原:多分、今までだったらサマソニのあの大きいステージで、あのスピーチをすることはきっと避けられていたと思う。SNSですぐ広まる時代だし、LGBT法案が通ってない国だし、ポリティカルな発言はあまり良しとされていない風潮がある。そんな背景があるなかでも、そのときのRinaは自身のステージをさらにいいものにしたいというパワーで動いていたから、自分が全力で支えてあげていくべきだと思ったし、スピーチを止めるのではなくてどういうふうに話すのがいいのか一緒に考えることだと思ったんだよね。Rinaのそのままを日本でしっかりと伝えていくことが、何よりも大事なことだった。

竹田:価値観の翻訳みたいなものが洋楽の役割だと思ってて、こういった発言や、政治や選挙について、分かりにくいから避けていたけど、アーティストが言っていたら興味を持つリスナーもいると思うし、勇気づけられることもある。
笠原:日本ではそういった社会的な発言をすると叩かれてしまうことがあるけど、洋楽のアーティストって、それを言うのが当たり前。基本的に本国ではそのまま加工せずに人へ伝わっているわけであって、日本でもその温度感で存在してもらいたいなと思う。私は洋楽の部署にいたからこそ、そこの部分は積極的に発信したいなと思っていました。
竹田:それこそ、前はみんなヒットチャートを聞くみたいな感じだったけど、今って人それぞれの音楽を見つけられる時代で、音楽性だけでなく、自分の気持ちを言葉や音楽で表現してくれるような人や、自分と同じ意見を持つ人など、自分が応援したいものや聞きたいものが取捨選択できる。洋楽のそういった価値観をどんどん輸入して広めていく役割が私たちにはあるよね。
ー最後に、今後の音楽業界はどのようになっていくべきだと思いますか?
笠原:何度か出てきている話だけど、華やかな業界だからこそ、自分の信じたいことや、大切にしているものを守った形で仕事を進めていくのが重要なのかなと思いました。やっぱり日本は社会的にも音楽的にもガラパゴス状態が続いていて、洋楽市場もどんどん縮小してしまっています。今はそれでいいかもしれないけど、長い目で見たときに大変なことになってしまう。だからこそ、音楽を通していろいろな考えを輸入したり、もしくはこちらから輸出したり。フレキシブルな体制になっていくほうが、もっと豊かに仕事ができていくと思うんです。そういった意味でも、国内の人たちはオープンになっていてほしいし、海外も受け入れる体制がオープンであってほしい。それが業界的に浸透していけば、日本のアーティストが海外進出するようになったり、世界で活躍するアーティストたちをもっと日本でも紹介できたり。いろんな可能性が広がっていくと思うんです。
竹田:有名だとか、売れて消えただとか、Spotifyの再生数だとか、数字や表面的な部分でアーティストを見がちだけど、支持のされ方ってそれだけではないですよね。現場で感じるのが、アーティスト自身が何をやりたいのか、どうして音楽をやっているのかを問い続けないと、燃え尽きてしまうこと。だからこそ、周りにいる人たちもそれを理解しないといけないし、考えていかなきゃならない。その理屈を抜いたら、ただ売れるためだけにやることになって搾取することになりかねないと思うんです。
笠原:やっぱり、いいものの尺度は人。いいとされるものは日々変わっていくし、変わるんだよというマインドで、作る側も、受け取る側もその気持ちを持っていてほしいなと思います。
竹田:音楽ってやっぱり新しい価値観と出会うきっかけの一つ。聞くほうも表現するほうも、自身を制限することが世界を制限することに繋がると思うので、そういう意味でも柔軟性を持ち続けることが大事ですよね。

















