「目の前にいる人が生きづらさを感じている現状に加担していないですか?」と、橋本ロマンス演出作品である舞台「Pan」は、観客に問いかける。今年の2月11日(土)に愛知県芸術劇場で再演された「Pan」は、東京で生きる若者の不安や孤独を描いた作品だ。「PAN」とは、ギリシャ語で「全て」を意味する。
※動画が見られない方はこちら
023.2.11「PAN」全編映像
PUMP management所属のモデルを含む8名の役者による本作品には、観客として見ている人自身が、舞台で描かれている状況に直面しているかのような危機感や焦燥感を与える迫力がある。これはロマンスが舞台演出をするうえで意識している「劇場で起こっていることと、劇場の外をどれだけ地続きにできるか」という挑戦によるものだろう。ロマンスが既存の劇場、作品、価値観に対し、問いを立て、演出を通してアプローチし続けるのは、ロマンスのこれまでの人生、そしてコロナパンデミックが浮き彫りにした「特権性」がきっかけだった。

大人に絶望していた幼少期に出会ったミュージカル
ロマンスは1995年に東京都で生まれた。保育園に通っていた頃から、遊ぶ時間やお昼寝の時間などの規則や、幼い子ども同士でも起こる同調圧力を強いられる環境に居心地の悪さを感じていたという。この居心地の悪さは小学校に入学した後も変わらず、「私はなんで今ここにいるんだろう」と違和感を持ち、常に疑い深かったと振り返る。さらに、家庭環境もロマンスの他者に対する疑心を強めていった。
「両親の仲が良くなくて、さらに当時は二人とも自分のことで精一杯だったのもあり、私の味方でいてくれる状況ではなかったんです。家が一番安心できる場所であってほしかったんですけど、うちは真逆で。一番緊張するし、安心できないし、気が抜けない場所だったんです」

ロマンスが幼少期に体験してきた不安感や孤独感は、周りの同級生の家族仲を目の当たりにするたびに増し、次第に周囲に負けたくないという思いが強くなっていき、学歴や経歴といった外からの評価をモチベーションに過ごしていたという。そんなロマンスが初めて大人に対して憧れを抱いたのは6歳の頃に父親が買ってきたミュージカル「CATS」のオリジナルキャスト版のビデオを見たときだった。
「私のなかでは大人は醜い存在で、私もいつかこんなふうになってしまうのだろうかと思って絶望していたんです。そんなときに『CATS』のビデオを見て、『こんなに美しい人間もいるんだ』と衝撃を受けて。私もそんな人間になれるかもしれないと思い、9歳の頃にミュージカル劇団の体験に行き、入団しました」
自由な環境で生まれた「橋本ロマンス」という新しい人生
家や学校で居場所を見つけられなかったロマンスにとって、劇団は救いのコミュニティになっていた。しかしロマンスの「幸せな家族像」によるコンプレックスから生まれた、外からの評価を求める傾向は中学時代も続いたという。志望校に推薦で入学できるよう、1年生の頃から着実にプランを組み立て、委員長や生徒会長を務めた。しかし、この頃も周りの生徒に馴染むことができず、優等生として他の生徒から距離を置かれていたという。その後、晴れて志望校に合格したロマンスは、高校時代が自分の人生のターニングポイントの一つだと語る。
入学した高校は帰国子女やバイレイシャルの人が多く、それもあってか自由な校風だった。ずっと窮屈な思いをしていたことから、その反動で自由な環境をロマンスは求めていたのだ。
「公立中学は自主性を育んだり、多様な選択肢を与えてくれる環境ではありませんでした。先生の言うことが絶対で、疑問を持つことさえ許されない。疑問を持ったところで、建設的に話し合ったり、改革するプロセスも用意されていなかったりすることが納得できなかったんです。でも、私が入学した高校では生徒総会がちゃんと機能していて。変えた方がいいと思うことがあれば、民主的に多数決を取って、そこで可決されたものはしっかり変わっていく。実際に在学中に女子生徒でもスラックスを履けるように校則が変わったりもしました」


多くの学校にも生徒総会は存在するが、実質機能していないものがほとんどではないだろうか。これは生徒自身が疑問を持っていても「変わるはずがない」といった諦めや絶望が故だろう。しかし高校時代にシステムに対して疑問を持つことや、声を上げること、変革の成功体験を得たことによって、ロマンスの社会に対する解像度は一気に上がっていった。またロマンスはこの頃から「橋本ロマンス」を名乗るようになった。
「当時美輪明宏さんに影響を受けていたんですけど、美輪さんが『名前は大事』と本の中で言っていて。自由な環境で新しい人生をここから歩んでいきたいと思い、通学中に思いついた『橋本ロマンス』という名前を、入学して1週間後くらいにクラスのホームルームで発表しました。『私は今日から橋本ロマンスです。ロマンスって呼んでください』って言ったらみんなすぐに受け入れてくれたんです。テストの回答も橋本ロマンスで通っているくらいオフィシャルで(笑)。高校時代は今の私を作ってくれた、立て直してくれた3年間でした」
模索し続けた先に見つけた「身体」というツール

当時もミュージカル劇団に所属していたものの、この頃からロマンスは役者ではなく演出に興味を抱き始めていた。それはロマンスの「自分自身がメッセージを作っていく側になりたい」という思いからのものだった。そして高校2年生の頃にオーストラリアに1年留学。演劇やダンス、ミュージカルが授業で学べる学校で多様な表現を吸収したロマンスは、帰国後現代美術の道へ進むことを決意する。その後美術系の大学に進学し、楽器やプログラミングを用いた作品などを課題で制作し続けたが、「自分の表現には一体何が合っているんだろう」と模索し続け、たどり着いたのが「身体」だった。
「大学時代は造形作品を作っていたんですけど、いろいろ試しているうちに、自分の身体が一番未知なんじゃないかって思い始めたんです。そう意識し始めたら、身体の動かし方も、習い事としてミュージカルをやっていたときとは全く見え方が違くて。一番近くに一番未開拓な部分が残っていたんだと思うと、すごく新鮮で驚きに溢れていたんです」

身体を使うダンス作品でパフォーミングアーツ(舞台芸術と訳されることが多い)を制作したいと思ったロマンスは、21歳にして振り付けをするためにダンスを学び始めた。ダンスを始めるのには遅いと言われる年齢だが、「できないとやらないは違う。私はちゃんと学んだうえでやるかやらないかを選びたい」という強い思いがそこにはあった。
その頃、通っていた大学は自分の作りたい作品を自由に作らせてもらえる環境ではなく、フラストレーションが溜まり、講師との意見の違いをきっかけに中退。より深くダンスやパフォーミングアーツを学ぶため、憧れの振り付け師が持つダンスカンパニーに所属した。しかし、幼少期からダンスをしていた人たちに囲まれる環境に葛藤する日々が続いたという。
「ダンスを始めるには遅い年齢というのもあったんですけど、周りはすでにプロレベルで、そのなかで自分も価値があることを証明したいって変に思ってしまったんです。そのせいでカンパニーの人を傷つける発言もしてしまって。でもそれをきっかけに、私が本当にやりたいことはダンスなのかっていうのをカンパニーの人も問い直してくれたんです。私は憧れの振り付け師の仕事を知りたくて入ったっていうのが元々の動機で、ダンサーを目指している人たちと一緒にやっていくのは無理があったんだってことをそのときに自覚できました」
この気付きをきっかけに、ロマンスはダンスカンパニーを退団し、本格的に自分の作品を作っていくことを決意した。
劇場の「中と外」をどこまで地続きにできるのか

ロマンスの作品には人の持つ絶望や恐怖、現代社会に対する違和感が色濃く映し出されている。2021年に上演された「デビルダンス」ではコロナパンデミックを通して浮き彫りになった社会構造や、未知のウイルスに対する恐怖を、自らの魂と引き換えに悪魔と契約する物語「ファウスト」、「ダンスマカブル*1」、映画『時計仕掛けのオレンジ』、そして江戸時代末期に起こった民衆運動「ええじゃないか」をモチーフに描いた。
「コロナ禍を通して、私たちはこんな地獄に住んでいたのかっていうことを思い知らされました。いろんな情報が行き交い、どの情報を信じるかで分断も生まれて。この価値観の違いはもともとみんなが持っていたものだと思うけど、コロナウイルスという一つのメジャーみたいなものによってすごく可視化されたなと思いました。そうしたときに圧倒的に弱者の立場に立たされてしまう人が存在するんだということが一気に見えてきたんです。このときの衝撃で『デビルダンス』という作品を作り、それ以降は社会に対する解像度が一気に高くなり、あらゆる現状を無視できなくなってきて。そうなったらとことん見ていくしかないと思い、それ以降は社会との接続を作品を通して試みるようになりました」
※動画が見られない方はこちら
舞台芸術を始めてからロマンスは疑問に思っていたことがあった。それは「舞台で行われていることと、劇場の外で起こっていることにギャップがある」ことだ。確かに舞台芸術に対して、非現実的であったり、芸術美を追い求めたものというイメージは多くの人が持っているかもしれない。こうしたイメージを生産している作品に対しロマンスは「そんなことをやっている余裕があることに特権性を感じる」と話す。
「自分の幸せが誰かの不幸のうえに立っているかもしれないっていう感覚がずっとあるし、正直それが事実だと思う。それを無視して自分だけ楽しいなんて、私は考えられません。ずっとミュージカルという非現実的なショーケースをやってきて、舞台で起こっている煌びやかな世界と劇場の外の世界のギャップを感じてきたからこそ、次は劇場の中と外をどこまで地続きにできるのかっていうことに使命感を持っています」
(*1)中世ヨーロッパで人種差別や流行病によって情勢が不安定になった際に、不安や恐怖により躍り狂う人が続出した現象。また、どんな階級の人でも死んだら同じ骨になることを表す美術用語としても使われる。
特権構造ではなく一つの共同体を作る
「劇場の中と外を地続きにする」というテーマは2021年に初上演された「Pan」へと引き継がれていく。本作では破綻した社会構造を、東京を生きる若者の不安や恐怖、絶望とともに描いている。そこでは目に見えない大きな脅威によって作り上げられた差別構造によって、安心できる場所やコミュニティを見つけられない、見つけられてもそのなかでのヒエラルキーに苦しみ破綻してしまう不安定な現状が映し出され、見ている観客にも危機感を感じさせる。本作のストーリーや演出は古代ギリシャの劇場形式をヒントに得たそうだ。


Photography:Yulia Skogoreva
「もともと古代ギリシャの劇場って、丘の傾斜の下部に舞台があって、上部に観客席があったので、観客席から舞台の向こう側に自分たちが普段暮らしている街が見える作りになっていたんです。そうすると、舞台で起こっていることも自分たちと隔絶されたものではないことが分かる仕組みになっていたと知り、本来の劇場のあるべき姿だなと思いました。そして古代ギリシャでは『観客席にいることがアテネ市民の証』とされていたらしく、貧しく演劇を見に行けない人たちは市民として扱われなかったそうなんです。当時は観客席っていうのが特権構造を作ってしまう装置になっていたのですが、現代においては観客席にいる人たちを一つの共同体を作る装置として応用ができるんじゃないかと考えました」
劇場のあり方、舞台と観客席のあり方を問い直し、誰もが対等な空間を提案し、実践し続けているロマンス。今年の2月11日(土)に愛知県芸術劇場で行われた「Pan」の再演では、初演時よりも舞台と観客席の関係性をどれだけフラットにできるのか、「Pan」で描かれている目には見えない大きな脅威とは一体何なのかをより強く問いかけた。
「愛知県芸術劇場の舞台は床が上がったり下がったりする『せり』という昇降装置が備わっていたので、私たちの足場が不安定であることや、自分たちが立っている場所がいつ崩れるか分からない恐怖を演出として追加しました。また、本作の終盤に、『自分が幸せだったらそれでいいと感じてる人たちばかりだと、気付かないうちに戦争の足音が聞こえてくる』というストーリーがあります。出演者が兵隊となり怯えながら手をあげるシーンでは、客席側の照明を付けているんですけど、これは『目の前にいる人たちをそういった状況に追い込んでいるのは自分たちかもしれない』と思ってもらいたくて付け加えた演出です」
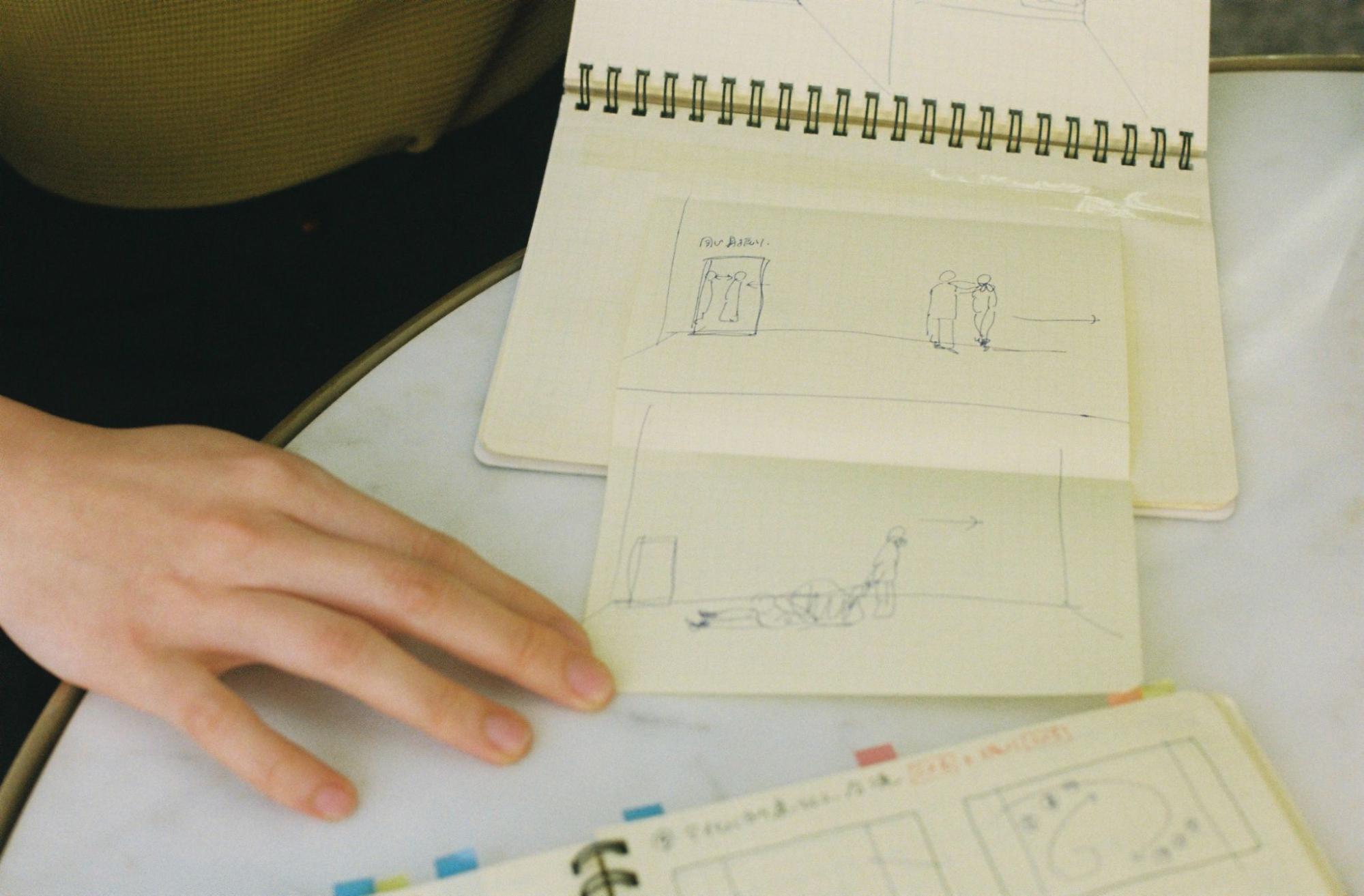
こうした舞台上だけでなく、客席までもを巻き込んだ演出は、「今目の前にいる人たちの生きづらさにあなたが加担している可能性はないですか?」というロマンスの問題提起なのだ。ロマンスの作品を見た人たちが持つ危機感は、こうした自分の持つ特権性や加害性と向き合うことによって生まれるものなのかもしれない。それはとても労力を使い、精神を削るプロセスかもしれないが、劇場に作品を見に来た人たちが少しでもその危機感を劇場の外へと持ち帰ることができたなら、劇場や舞台作品がロマンスの言う「一つの共同体」を作り上げる装置として機能することになるだろう。
私たちが力を入れるべきなのは、安全じゃない場所をどう減らせるか
どれだけ舞台で起こっていることが自分たちの現実の延長線上であるかを意識させるために、ロマンスはキャスティングや、キャストとのコミュニケーションも重要視している。
「現実離れしたキャスティングではダメで、その辺を歩いているような人がいいなと思っていたし、ダンスの経験がなくてもいいと思っていました。実際に出演者の半分はダンス未経験者です。そして表現することには責任が伴ってくると私は思っていて。私のやりたいことを忠実に演じることは、そのうちロボットでもできるようになってくると思うんです。出演者には人形になってほしくないので、この作品にとって必要な人を選ぶのではなく、この作品を必要としている人をキャスティングするようにしています。そのためにはキャストの意見を聞いたり、同意を取ったり、ヒアリングを重ねながら制作しています」

これはロマンス自身がこれまでに感じてきた舞台芸術の世界に根強く残る権力構造に対する違和感からくるものだ。多くの役者がプロデューサーや監督、演出家の期待に応えられなかったらキャスティングから外されてしまうんじゃないかという不安を持っている。こうした不安から権力構造はより強化され、自分は代替のきく存在であると常に恐怖心を募らすこととなる。こんな環境をロマンスは「不健康」だと話す。
「その人個人が経験してきたことや、その人のストーリーが必要なんです。それは替えがきくものではないし、私が求めることをうまくできなかったとしても、それはその人の価値とは全く関係ないし、今まで生きてきた人生を持ってこの場に来てくれるだけで十分だし、そのままでも価値があるということを、出演者には感じてほしいです。そのために稽古場での権力勾配を私自身がならしていき、意図的に出演者にこれはやりたい、やりたくないという選ぶ権利を与えています」

コロナパンデミックによって浮き彫りとなった弱者を生み出す社会、そして舞台芸術界での権力勾配。こうしたあらゆる不均一に直面してきたロマンスが作品や制作プロセスにおいて隔たりを埋め、均一にならしていくのは、「自分自身も誰かを脅かしているかもしれないと気付いてもらうことが私の役割」だからだと語る。
「セーフプレイスやシェルターのような場所は、本来必要ない状態であってほしい。現段階としてはそういった場所はとても必要ですが、同時に私たちが力を入れていくべきなのは、安全じゃない場所をどう減らしていけるか。ほとんどの場合、安全じゃない場所を作っている人たちって無自覚だと思っていて。そこを私は自分の作品を通して自覚的になってほしいなと思っています。あなたもこの問題の当事者なんだということを伝えるために、そこに説得力を持たせるために、『舞台だけで起こっていること』と言われないようにしなくてはいけないんです」
自作へと続く「全て」
現代社会で生きる絶望や恐怖、被害者性を見捨てず、同時に自身や社会、舞台芸術界の持つ特権性や加害性と向き合い続けるロマンス。これから制作する次回作のテーマを聞くと、「Pan」から続く「公共性」だと教えてくれた。
「『Pan』でも触れ始めているんですけど、みんなという存在は誰が誰のことを指しているんだろうと思っていて。みんなを作るときって、同時にみんなに含まれない人も生まれるじゃないですか。そこをより深く探究していきたいなと思っています」

自身の作品だけでなく、劇場のあり方、制作プロセスや業界の価値観など、あらゆる方向でアップデートを仕掛け続けるロマンス。こうした思いを持ち、一部の人しか持たない特権を全ての人が持つ権利へと分配していく演出家が、多くの問題を抱えた現代にいてくれることが救いであり希望である。しかしロマンスのみを変革者として讃えるのではなく、ロマンスが作品を通して伝え続ける「あなたも問題の当事者である」ことを常に考え続け、大きな共同体へと進んでいきたい。「全て」の人が、一部の人が持つ特権によって窮地に立たされない世界を目指して。

橋本ロマンス
1995年生まれ。東京都出身。(They/She)
コンセプチュアルな手法を用いながらも、ポップやストリートカルチャーの要素を取り込むことで多方面に訴える同時代性の高いパフォーマンス作品を制作する。
様々な文脈を分解しコラージュの如く再構築することで作品テーマを多面的に分析し新たな仮定を提示するスタイルが特徴。
作品を構成する全要素に一貫して高いヴィジュアル性がある。
自身の作品のプロデュース・演出・振付に留まらず、キュレーターや撮影ムーブメントディレクター、ステージングディレクターとしても横断的に活動を行う。
DaBYレジデンスアーティスト。

















