ついに最終回…!
この挨拶を書くのも最後、Joです!

本当に楽しい連載だったので、さみしいな!
この連載を始めたのが2020年の6月だったので、約1年間強連載させて頂きました。
もっともっと映画史を勉強したいと思って始めた連載だったので、私自身、知らないことをたくさん勉強させてもらいました。
そして最終回となる第6回、ついに、2000年代突入です…!
映画が現実に負けた日
突然ですが、みなさんは映画に何を求めていますか?
現実逃避?
刺激的なスリルやロマン?
人生のサンプル?
十人十色な答えがあると思います。
基本的に映画はフィクションといわれる”作られた物語”です。
日常では味わえない刺激を求めて映画を観る人も多いのではと思います。
2001年に起こった9•11(アメリカ同時多発テロ事件)。
世界貿易センタービルに旅客機が突っ込んでいく映像は、あまりにも強烈でした。
私たちの日常が、映画というフィクションを超えた瞬間。
非現実的な現実がTVの中で何回も繰り返し放送される。
当時の人々にとって強烈な刺激だったと思います。
映画は9•11の映像から私たちが経験してしまった強烈なイメージを超えられないのではないか、という議論もいまだに目にしますし、私たちの記憶に深く深く刻まれる映像だったのではないかと思います。
ドキュメンタリー映画の隆盛
もともとドキュメンタリー映画というジャンルはありましたが、9•11以降、製作者が増えたと言われています。
その一つにあげられるのがマイケル・ムーア監督が作った『ボーリング・フォー・コロンバイン』(2003年公開)。
同作はドキュメンタリーとしては異例の大ヒットを飛ばします。
※動画が見られない方はこちら
コロンバインというアメリカの田舎街でおきた高校生による銃乱射事件を題材に扱っています。
この銃乱射事件をおこした18歳の少年2人が、マリリン・マンソンを聞いていたという事実から「マリリン・マンソンが青少年に悪影響を与えている」と訴える保守派に対し「少年たちは乱射事件の直前までボーリングしてたらしいけど、ボーリング場は悪影響じゃないの?」というのをテーマに据えたドキュメンタリーです。
テーマを聞いただけでもすでに面白い。
本作、監督が直接アポなし取材を試みたりしているのですが、シリアスなテーマの中にちょっとしたコメディ要素も入れてて、観ている人を飽きさせないようにしようと努力する監督本人の律儀な性格を感じる作品でした。
この乱射事件は映画監督であるガス・ヴァン・サントも題材として取り上げ、『エレファント』(2004年公開)という映画を作りました。
※動画が見られない方はこちら
これは『GERRY』(2002年公開)『エレファント』(2004年公開)『ラストデイズ』(2005年公開)と続く三部作の一作品として作らていて、三つの作品に共通しているテーマが「日常に起こる死」です。
どれも映画史に残る名作ですが、とくに『エレファント』は必見です。
めちゃくちゃ美しいロングカットのシーンで全体が構成されています。
そして主人公だけではなく、いろんな人の視点から映画が作られていて、カメラの動きによって視点が移り変わるというのがとてもわかりやすく描かれています。
このカメラのスムーズな動きを真似したくて、学生のころ、いかに手ブレせずにカメラを持ちながら歩くか、というのをひたすらに練習していました…(笑)。
なので、実はわりとカメラを手ブレせずに持って歩けるというちょっとした特技があります(笑)。ちなみに思っているよりも腰の位置を低くして歩くというのがコツです。学生のみなさまぜひやってみてください!
ちなみに、本当の撮影ではステディカムという身体に装着する三脚を使用します。
この三脚自体が重いので、けっこう大柄な男性が多い印象です。


(お仕事ご一緒させてもらったステディカムオペレーターの岩井さんからお写真お借りしました!)
ステディカムオペレーターの方は撮影が終わるとすぐ座ることが多いので、見た目以上に体力使うんだろうな、といつも思います。
『エレファント』は映像の美しさもさることながら、複数の視点で物語を捉えるという意味で、個人的にとても影響を受けた作品です。
この映画史の連載で紹介した作品の中で一番おすすめの作品かもしれません。
ぜひ観ていただきたいです。
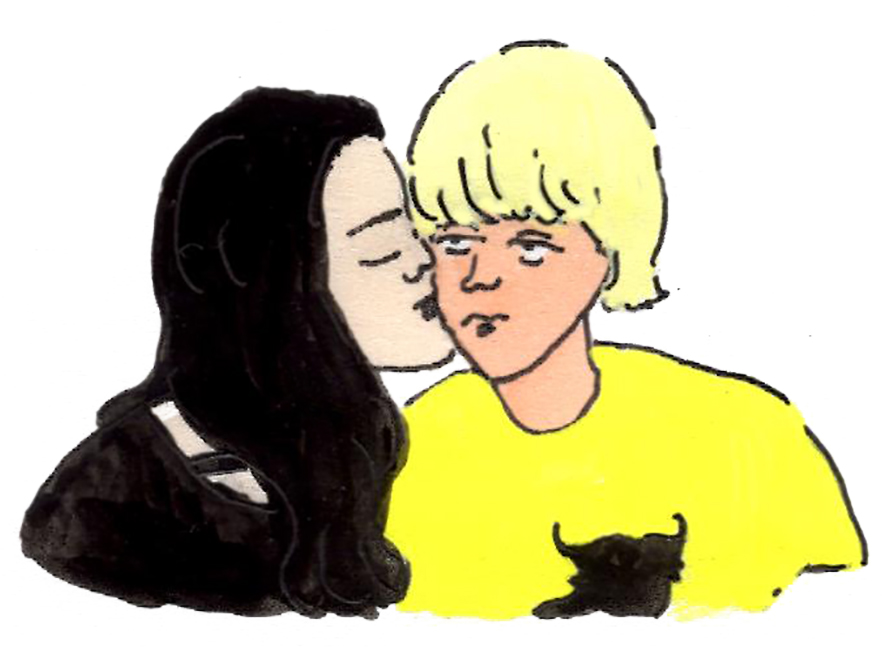
エンタメ化するドキュメンタリー
9•11を経験した映画制作者たちは、リアリティってなんだろう?という本質的な問いに直面しました。
よくドキュメンタリー作品を扱ったテレビ番組でも「やらせ」かそうじゃないか議論が取り沙汰されたりしますよね。
個人的にはドキュメンタリーはそもそも、全てがリアル(ありのまま)ではないと思っています。
撮影した映像を編集という作業で切り繋いで一つの作品にしている以上、そこには何らかの作為が生まれます。
何がフィクションとされて、何がリアルなのかという議論をたびたび目にしますが、あえてその議論を逆手にとってドキュメンタリーをエンタメ化した、映画史に刻まれたドキュメンタリー作品を紹介します。
ドキュメンタリーの体で撮影されたフェイク・ドキュメンタリーのことをモキュメンタリーと呼ぶのですが、ブレア・ウィッチ・プロジェクトというホラー映画を皮切りに盛んにホラー映画制作に取り入れられるようになりました。
ブレア・ウィッチ・プロジェクトは「魔女伝説の真相を調べに森に入ったまま消息を絶った学生3人が撮影したビデオテープを森で発見した」という内容で広告されました。
モキュメンタリー映画は他にもありましたが、このブレア・ウィッチ・プロジェクトがなぜ革新的だったかというと、広告の一貫として、Websiteを立ち上げたり魔女伝説についての書籍を販売したりして、フェイクストーリーを真剣に、そして多角的なアプローチから作り上げた点にあります。
※動画が見られない方はこちら
興行的にもブレア・ウィッチ・プロジェクが大ヒットしたため、続くようにパラノーマル・アクティビティ、クローバー・フィールドなど、モキュメンタリー手法を使ったホラー映画が制作されました。
この辺の作品は、ドキュメンタリーの体として撮影しているので、監視カメラだったり、iPhoneやホームビデオカメラで撮影された風だったりという撮影技法を用いているのが特徴です。
なのでめっちゃ怖い(笑)。
なんか自分の身にも起こりそうで、怖い。自分の携帯のカメラロールにもこういうの映り込んでたらどうしよ、とか思っちゃいます(笑)。
そして2000年前後にかけて、リアリティショーという番組形式が盛んに制作されます。
リアリティショーとは、一般人に密着してその人の生活ぶりを面白おかしく番組として伝えるというもの。
密着取材するジャンルは家族、恋人、警察官など多岐に渡り、日本でも爆発的な人気を収めた番組が「あいのり」です。
パリス・ヒルトンやキム・カーダシアンなどはこのリアリティショーにセレブの生活を見せるという番組で登場しており、そこで更に世界的に有名になったセレブとも言えます。
ちなみに日本けっこう面白いドキュメンタリー多いので、2本紹介させてください。
「A」森 達也 監督作品
※動画が見られない方はこちら
こちらオウム真理教の信者に密着したドキュメンタリー。
地下鉄サリン事件のほとぼり覚めぬうちから密着しているので、かなり内容が過激とおもいきや、とてもほんわかした信者たちが描かれています。
ていうか、めちゃくちゃにイノセントで繊細な良い人たちという印象さえ抱きます。
メディアで悪者として描かれている人たちって本当に悪者なの?という、多角度的な視点を与えてくれる傑作です。
続編の「A2」もあるので、合わせてぜひ!
「ゆきゆきて神軍」原 一男 監督作品
※動画が見られない方はこちら
こちらは映画史に残る名作と言われてます。
極左翼の男性に密着した作品で、前科もあるのですが、この男性も変わってるけど、実直でなんだか良い人なんです。
個人的にドキュメンタリーはインタビュアーである監督の人柄が本当に色濃く反映されると思っていて、被写体をどう扱っているかが如実に作風に影響するので、その監督自身の人柄が好きかどうか、というところが非常に大きいと感じています。
今まで会った日本のドキュメンタリーの監督達(そんな多くはないですが…)みんな、良い意味でゆったりとした人が多かった印象です。
テキパキしてる人って、ちょっと自分の話をしにくいというか、こっちもテキパキ話さなきゃっていう気持ちにさせられるので、ゆったりとしたペースの方が相手も心を開きやすいんだろうなと思ったりしました。
逆に海外のドキュメンタリー監督はテキパキ話す印象です。
映像でしか見たことないですが(笑)。
マイケル・ムーアとか、すごくテキパキ話す感じ。
オリバー・ストーンもわりとビシッ!バシッ!と話す印象があります。
監督の人柄という意味でいうと、最近とっても素敵だなと思った作品が「ハイパーハードボイルドグルメリポート」という上出遼平監督の作品でした。
※動画が見られない方はこちら
大人気作品なので、見た方も多いと思います。
過激な内容ももちろんすごいのですが、監督の人柄が真摯で、見ていてとても心地よいなと感じました。
俗に言う「ヤバイ」と言われてる人たちや「悪者」とされている人たちに接する態度を観ていると、自分もこういう人でありたいなと、襟を正す思いです。
刺激的な映像の中に、被写体の人間的な部分をしっかり感じられる、とても素敵な作品でした、こちらネットフリックスでご覧頂けます。
すみません、流れで3本紹介しちゃいました(笑)。
飛び出す映画たち
3D映画は1950年代あたりから実はあったのですが、赤と青のフィルターがついたメガネのようなもので、ちょっと立体的に見える、くらいのものだったそうです。
映画ではないですが、ちょっと前にトーマス・ルフというフォトグラファーが3Dの写真作品を発表していて、思っている以上に浮き上がって見えて普通に感動しました(笑)。
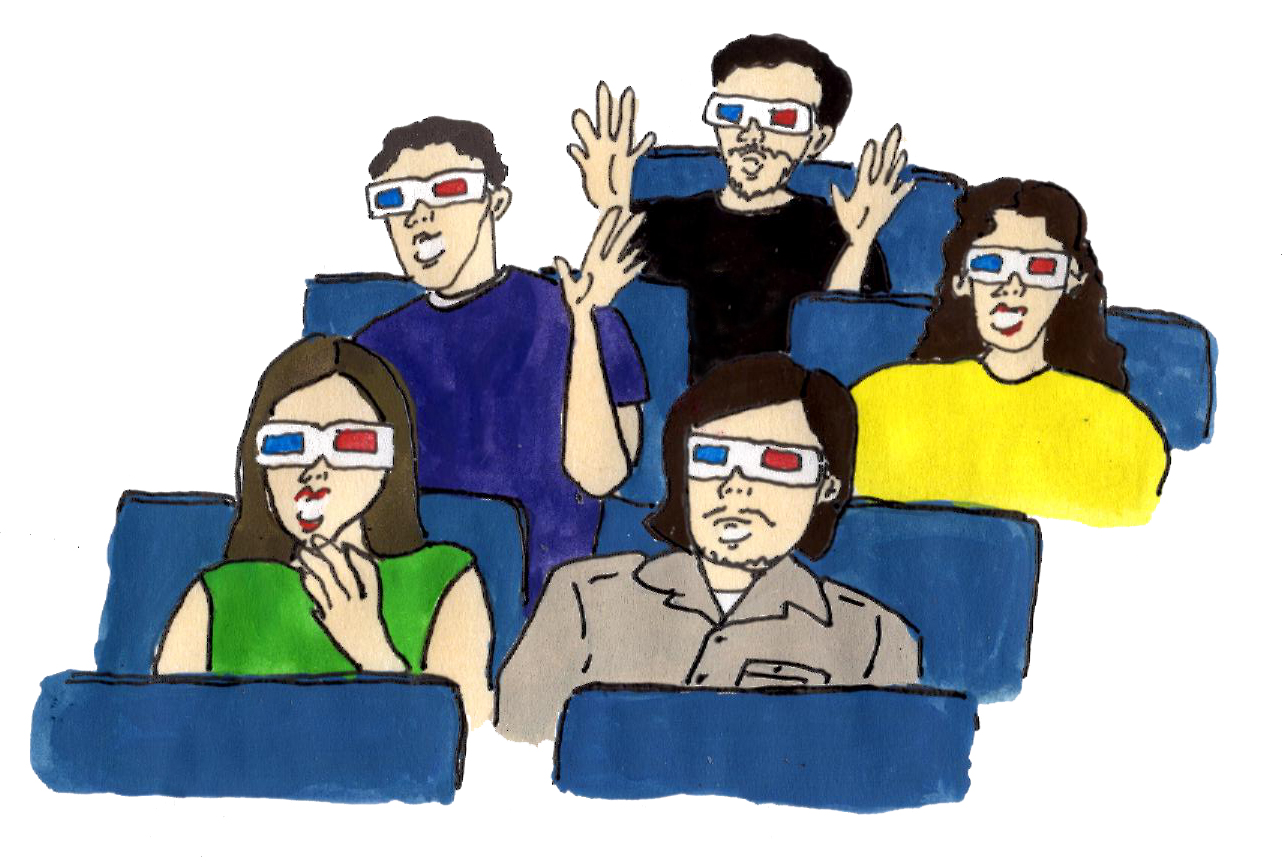
時代をすこし遡りますが、なぜ1950年代に3D映画が作られたかというと、家庭用テレビの登場がきっかけでした。
当時のテレビは高級品だったので、全ての家にあったわけではありませんが、テレビの登場により、映画館へ人々が来なくなることを懸念して、家では出来ない体験を映画館で提供しようと始めたのが3D映画の起源らしいです。
最近は3Dに加えて4DXシアターも出てきました。
椅子が揺れたり、風が吹いたり、水が飛んできたり。
見たことある人もいるかと思いますが、観てる側もあちこちに反応しなくてはいけないので、大忙しですよね(笑)。
この3Dメガネをかけて飛び出す映画を観る技術が飛躍的に上がったのが2000年代と言われていて、2005年にディズニーが『チキン・リトル』を3D映画として公開し、そこからさらに3D映画として爆発的ヒットとなったのが2009年公開の『アバター』でした。
※動画が見られない方はこちら
アバターは製作当初から3Dで観ることを前提として作られていたので、それが話題となり前売り券の90%は3D上映のものだったそうです。
公開当時、わたし映画館でバイトしてたんですけど、本当に大変だったんだよな…。
思い出話になっちゃうんですけど、当時、3Dメガネはまだ新しい技術だったので、メンテナンスが大変で、グラスが割れたり、途中でバッテリー切れしたり、なにより、観賞後の3Dメガネを専用シートで吹くという作業が本当に大変でした…。
ちなみにアバターは現状、歴代世界1位の興業成績を誇る映画です。
総売上約3100億円。驚異的な数字ですね。
今はもっと手軽に3D観賞できるところも増えましたね!
基本的にはレンタルではなく、3Dメガネを100円くらいで購入という形式が増えたので、劇場スタッフの作業量の軽減にもつながったと思います。
3Dも4DXも、今はまだ発展途上の技術なので賛否がありますが、VRの登場により、今後、一層この映画をフィジカルに体感していく技術というのが発達するのだろうなと思っています。
昔、通ってた美術予備校で、みんなで他人の絵を観ながら「お前たちはこの絵の中に入り込んで、そこに座れるか?」ということを講師に言われました。
その言葉は今でも自分の物づくりの根幹だと思っています。
私が作った作品の中に、視聴者が入ってこれるか、そしてその映像の中でひとりのストーリーを語るものとして存在することが出来るか。
いつもどうすれば良いか迷った時に立ち返る質問として、大切にしています。
作品を観るときも、その作品の中に入って、座って、あたりを見渡したり、製作者たちの人生の中に入って、同じテーブルに座って彼/彼女らの人生に入り込めるか、というのを自分の「好き」のベクトルにしています。
なので、フィジカルに映画世界を体感する(映画が視聴者に近づいていく)のではなく、メンタルで映画世界を体感する(視聴者が画面の中に近づいていく)っていうのが、一番力強いコミニケーションなのでは、と個人的には思います。
消えていくフィルムたち
ミレニアル世代は小さいころお家にフィルムカメラがありましたよね。
Z世代は多分、生まれたときからデジタルだったのではないでしょうか?
2021年に生きる私たちが普段観ている映像のほとんどがデジタルで撮影されたもので、フィルムで撮影されたものはあまりないと思います。
フィルムを好んで使う監督はとても多いのですが、コスト的にかなり高額になりがちなので、潤沢な予算があるような大型作品でないと撮影が厳しいのが実情です。
そういった理由から、私も含め、若い世代はフィルムを見たこともないし、フィルムで動画を撮影したことがない人がほとんどだと思います。
わたしも最近、初めて35mmと16mmフィルムの動画撮影を経験しました。
是枝監督や、クリストファー・ノーラン監督はよくフィルムを使う監督として知られています。
亡くなってしまいましたが、先に紹介した『エレファント』の撮影監督であるハリス・サヴィデスもフィルムを好んで使っていたそうです。
ですが、このデジタル技術革新の流れは止まらないと思うので、やっぱりフィルムは今後も少なくなっていくでしょうし、フィルムとデジタルで撮影したものの違いはもっと分からなくなっていくのだろうなと思います。
実は連載の第3回、マリリン・モンローの章でちらっとクイズを出したのですが、マリリンが映画『七年目の浮気』の中で主人公リチャードと『大アマゾンの半魚人』という映画を一緒に見たというシーンが描かれています。
こちらを見ると、ちらっとポスターも出ています。
このポスター、なんか見覚えある人いませんか?
※動画が見られない方はこちら
この『大アマゾンの半魚人 』、2018年にギレルモ・デルトモ監督が『Shape of Water』という名前でリメイクし、アカデミー賞を受賞しています。
※動画が見られない方はこちら
なのでこの『大アマゾンの半魚人』は実に3作品の映画にそれぞれ形を変えながら受け継がれています。
ギレルモ・デルトモ監督もCGを多様した作風で知られる監督なので『Shape of Water』はかなりCGが使われていますが、この『大アマゾンの半魚人』はそういう意味で、フィルムとデジタル、両方の技術で描かれた作品とも言えますね。
ピクサーのように完全デジタルで制作される作品も増えています。
ピクサーは元々、第4回で登場したジョージ・ルーカスが作ったルーカス・フィルムのデジタル部門でしたが、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブスがその部門を買収し、ピクサーと名付けました。
ピクサーの映画の一番はじめに登場する電気スタンドのキャラクターいますよね、あのキャラクターにはルクソーJr.という名前がつけられてるらしいです。
※動画が見られない方はこちら
ピクサーは作品自体が評価されることが多いですが、レンダーマンというPCソフトを独自に開発していたり、とても綿密なマーケティング戦略を組むことでも知られています。
作りたいものを作るために、今ある技術では不具合があるから、自分たちで作る。
その上で、それをきちんと消費者に届けられるようにどうすれば良いか考える。
ただ良いものを作るだけではなく、作る前の段階と作ったあとの段階をきちんと設計しているところにとても好感を抱きます。
ロマン(夢)も大事ですが、ソロバン(資金回収)もきちんと考えるというのは今後のクリエイターにとって必須スキルと思うので、美大や専門学校でもっとそこの教育を充実させた方が良いんじゃ無いかと個人的に思います。
お金の話は汚い話、というような間違ったイメージや、守銭奴、清貧というような言葉があるので、お金の話と政治の話をなかなか普段の生活ですることはないかもですが、だからこそ私はすごくカジュアルにお金と政治の話を日常生活でするようにしています。
なぜこんなにお金の話をしているかというと、単純にお金がないと作品が作れないし、生活出来ないからです。
もちろん、低予算の撮影で、お友達にお願いして協力してもらったりすることはあるかもしれませんが、そればかりだとお互い生活していくことが出来ません。
作ることを仕事にしてお金をもらい、生活していったり、家族を養ったり出来なければ、その仕事自体が破綻してしまいます。
そうすると、「あの業界は稼げない」という理由からその業界で働く人が減り、ひいては業界全体が先細っていって最終的には潰えてしまいます。
なので、積極的にお金のはなしをすること、お金の教育をすることは、とても大事なことだと感じています。
コンテクストを作り直す
こちらが映画史を語る最終章となります。
映画史的にはもっと説明すべき流れや文脈がたくさんあるのですが、この連載では、みなさんが映画を見る時の参考になる程度の触りだけを説明するという目的だったので、省きまくった部分が多々あれど、これだけは逃せないという作品で締め括りたいと思います。
2021年3月に公開された『シン・エヴァンゲリオン』。

この作品、みなさんも知っているように1995年に公開された『新世紀エヴァンゲリオン』を庵野秀明監督自ら作り直したもの。
『新世紀エヴァンゲリオン』は1995年当時、社会現象になるほどの人気作品で、アニメ史はもちろん映画史的にも、そして日本文化史としても外せない一作となりました。
庵野監督は特撮・アニメ好きでも知られており、エヴァンゲリオンの作品内でも特撮的なアングルや、『ガンダム』や『超時空要塞マクロス』を思わせるような描写が出てきており、それまでの日本アニメ、日本映画の文脈をちりばめた作品でもありました。
そして自らが作り出したエヴァンゲリオンという文脈を、2000年代に新しく『シン・エヴァンゲリオン』という形で作り直し、新たな文脈にしたというのが本当に斬新だと思いました…。
監督が、自分が作った作品の続編を作ったり、未完だった作品を完成させるために作り直したりなどはありますが、完成した作品をこの規模で作り直す、というのは非常にレアケースです。
そもそも大ヒットしてないと”作り直し”に対して予算が出ないので、ヒット作品を持っている監督にしか許されない行為だと思うと、そういう部分も含めて本当に凄すぎる、と思いました。
ちなみに今回の新シリーズである『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』、個人的にはパラレルワールドという設定なのだと解釈して見ていたのですが、パラレルワールド作品を見るときのポイントが実はあって、「何が運命だったのか」に焦点をあてて見るととても面白いのです!
パラレルワールドやタイムマシン系の作品、例えば、何度も同じ日を繰り返す『ひぐらしの鳴く頃に』や、時間を遡ることが出来る『TENET』などはこの「何が運命だったのか」を探りながら観るととても面白いです。
自分の人生を何度もやり直そうとする主人公達が、何度やり直しても変えられなかった運命は何なのか、それを見つけると作品の深みが増します。おすすめの観賞方法です!
あとがき
実は、この第6回が一番書くの大変でした…。
ここまでの回は、“誰がどの作品に影響を受けているのか”が明確な場合が多く、参考資料も分かりやすくて紹介しやすかったのですが、2000年代に入ると、非常にそのあたりの解析が難しくなってくるんです。
個人的には、ネットが流通したことにより、製作者が超膨大な様々な情報から影響を受けているので、特定が難しいという点があると思っています。
しかも参考資料が、私たちが日常的に撮影しているInstagramのストーリーやTwitter、Tik Tokなど、プロではない人たちが撮影したものをソースにしていることもあるので、もはや特定がしずらい。
それ自体が新しい映画史・映像史であると言えます。
私たちの映像が、誰かの映像に影響を与えている。
私たちの全てが、誰かの何かに繋がっているんだと思います。
巨匠監督やアーティストが作る作品の中に、もしかしたらこれを見てくれているみなさんのエッセンスが入り込んでいるかもしれません。
私がこれから作る作品の中にも、もししたらみなさんのエッセンスが混じっているかも!
そう思うと、少しだけ世界が違って見えますよね!
そして、この連載を書かせてくれた編集長のJun、いつもすっごく丁寧に編集してくれたNoemiさん、超可愛いイラストを描いてくれたMokaちゃん。
みんなのおかげで、宝物みたいな連載が出来ました、みんなの優しさずっと忘れないです。
そして最後までお付き合い頂いた、これを読んでくれている映像フリークなみなさま、本当に本当にありがとう!
とっても楽しい連載だったので、おわってしまうのが悲しいけど、お別れです。
最後の言葉は、北野武監督のこちらの作品から拝借させて頂きます!
エンディングの音楽がイケてる!!
『キッズ・リターン』
※動画が見られない方はこちら
また、いつか、どこかでご一緒しましょう!!
2021年 吉日
Jo Motoyo

















