なんでもかんでも、ハラスメント全般を「○○ハラ」とキャッチーな名前で呼ぶ昨今。ハラスメントが人権侵害であることを認識している人はどのくらいいるだろうか。「男だから、女だから」と勝手にジェンダーを押し付けられ、言い訳にされ、声を上げることを諦めてきた人はどのくらいいるだろうか。そして、それすらを考えたことも、疑問にすら思ったこともない人はどのくらいいるのだろうか。「セクハラなんて罪は存在しない」なんて発言をする政治家がいまだに国を動かし続けられているのは、なんでだろう。
ずっとこのような日本のジェンダー不平等の問題に違和感を抱いていた映画監督・舩橋淳(ふなはし あつし)が、現実の職場で起こったセクハラ問題を題材に制作した映画『ある職場』が3月5日より公開された。

セクハラは、「性差別」であるということ
大学を卒業後にニューヨークへ渡り、映画制作を学んだ舩橋淳(ふなはし あつし)。オダギリジョーの初海外進出作品となった『ビッグ・リバー』(2006)や、東日本大震災による原発事故で町全体が避難を強いられた福島県双葉町の人々を追ったドキュメンタリー映画『フタバから遠く離れて』(2012)などで知られる彼が、新たな作品の題材としたのが、職場でのセクハラ問題だ。『ある職場』と名付けられたこの作品は、実際にセクハラのあった職場の関係者、被害者、加害者に舩橋が取材を重ね、実在した事件をもとに、その後日談として創作されたフィクション映画である。

「これまでも、映画作家として“時代の無意識”をすくいとるようなものを撮りたいと作品と向き合ってきました。そのなかに日本社会のジェンダー不平等の問題があります。夫婦同姓の婚姻制度はもちろんのこと、LGBTQへの差別や雇用機会・給与の格差など挙げたらキリがありませんが、ジェンダーを取り巻くあらゆる社会のシステムに対して、ずっと問題意識を持ってきました。男性優位の思想をベースに持つ上の世代をずっと見てきたし、男性が女性に対してあり得ない発言をしているのを目の当たりにして、自分自身が声を上げられなかったこともある。こういうことを自分の世代で最後にしてゆくにはどうしたらいいんだろうって、ずっと考えながら生きてきたんです」
ジェンダー平等ランキングが156カ国中で120位の日本。少しずつ変わってきているとはいえ、ほとんどの女性は自分の“性”を意識しないで生活を送ることはできないし、もはやこれまで蓄積されてきた“女性のあり方”が染み込みすぎて、それすら感じたことがない人もいるかもしれない。いまだに企業の管理職には男性が多いこと、男女間賃金格差は依然として大きいこと、女性の就業率や就学率の低さ、性暴力…。“女だから”という理由で制限や圧力をかけられてきた人たちは、数えきれないほどいるはずだ。
「日本では、“セクハラ”ってグレーゾーンの言葉として捉えられているので、性差別だと認識している人が少ないと思います。企業でもセクハラ防止講座がありますが、『お酌をさせてしまってはダメ』『容姿のことを言ってはダメ』などが主な内容で。それを聞くと本当に絶望的な気持ちになるんですけど、そういった表面的なことで終わらせるのではなくて、根底にある『差別』について問いかけることで、問題を考えていけるような作品を作りたいと思ったんです。ただ、明日は我が身だとも思っています。『自分なら大丈夫だろう』『自分は差別なんてしてない』など、自分には関係ないという考えが、加害者にもなりうる可能性に繋がっていると思うので」
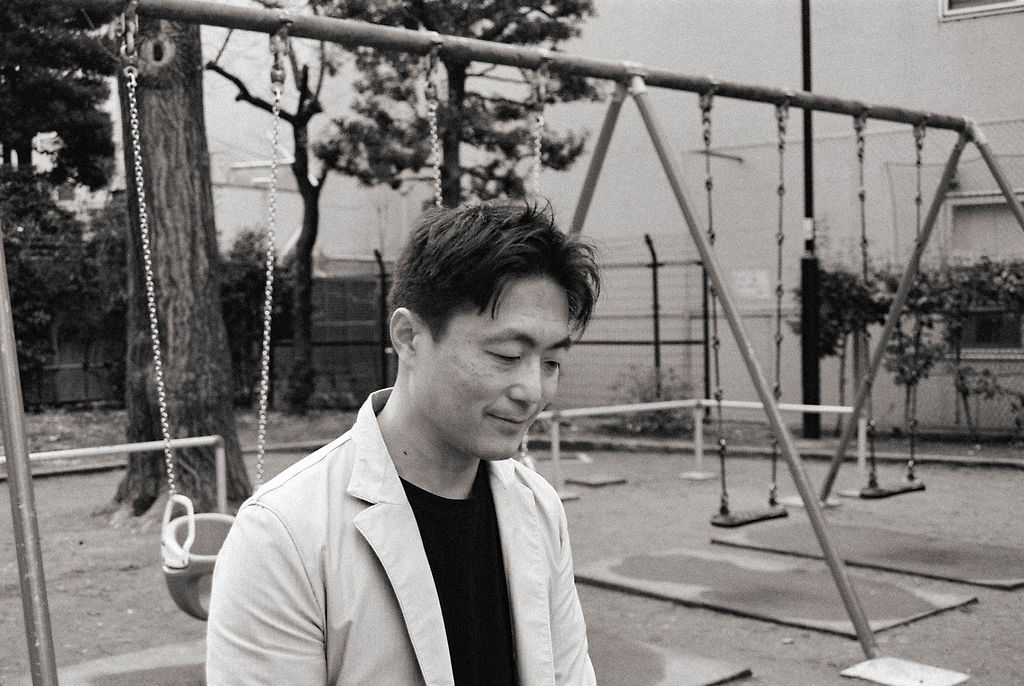
本音をぶちまけ合う、「ディベート映画」にした理由
当初はドキュメンタリーとして映画化をしようとしていたこの作品。実際に当事者たちを取材していく過程で、個人の顔出し・名前出しでドキュメンタリーを制作することは困難と判断。劇映画として作品化することにした。
ストーリーの舞台は東京を中心に全国展開をしている一流ホテルチェーン。女性職員が、密室で男性の上司にセクシャル・ハラスメントを受けた事件が瞬く間にホテルの内外に広まり、その女性職員やホテルはSNS上で誹謗中傷を浴びて炎上する事態へと発展。そんなぎくしゃくした職場の雰囲気にげんなりした職員の一人が、湘南の海辺にある社員用の保養所へ二泊三日の小旅行を提案する。みんなでリゾート気分を味わおうという企画だったが、これまでいろいろな立場の職員が事件に対して感じていた鬱積がじわじわと浮上し、それぞれが考える“正しさ”を振りかざしていく。


「こういった題材は、僕のような男性監督よりも女性の監督が作ったほうがいいのかなと思っていたんです。でも男性が声を上げるのも大切だなと思って。なので、どうやって制作をしていくかを考えたときに、女性の意見をたくさん反映させる映画の形態にしました。そのために、女性の考えを僕が台本に書くのではなく、女性が考える生の言葉を伝えていくべきだと思いました」
そこで舩橋が考えたのが、“議論をする”映画にすること。それぞれのキャラクター設定やキーワードのセリフはあるが、シナリオは存在しない。シーンごとにそれぞれのキャラクターを理解しきった俳優たちが自由に話すという即興的なスタイルで撮影をした。
「作品自体はあくまでフィクションなので、上司や部下などの立場は関係なくそれぞれの本音をぶちまける空間を作りたいと思いました。なので、フィクションの存在として会社の保養所を撮影場所に設定したんです。日本の職場では、何か問題が起きても空気を読むことが先行されて、みんな口に出さずに穏便に済ませようとする体質がありますよね。この映画はそんな体裁は取り払って、それぞれが本音を言い合うことで何が正しいのかを見ている人に考えてもらえるようなものにしたかったんです」
作中に登場するのは、「自分もそういう経験があるから」とセクハラを受けた女性職員を守ろうとする女性上司、「セクハラという犯罪はない、加害者はそこまで悪くない」と本音では思う男性の上司、「男社会は変わらないから我慢して自分でのし上がっていくしかない」と部署異動を促す女性上司、「こうして場を乱すことは彼女のわがままだ」と思う男性の同僚など。この社会の縮図を表したかのようなリアルな設定だ。
「それぞれのキャラクターは、これまでの取材をベースに、いろんな要素をミックスして考えました。演じてもらう俳優には、自身のキャラクターを正しいと本気で思うまで話し合いを続けたんです。撮影をするよりも、それぞれが自分の意見を正当化できるようになるまでを作り上げていく過程のほうが長かったですね」



カメラも舩橋が握った。互いの意見がぶつかり合うあまり、2時間ワンテイクだったことも。
「大体の流れはあるものの、誰がどの順番で喋るか、何を喋るかは決めてない。だから、誰かが泣き出したり、物凄い剣幕で怒ったり。どこから意見が飛び交うのかが想像できないんです。映画の途中でも話す本人に向かって、キャメラがグワっと移動する部分があると思うんですが、『この人、怒ってる!』と僕自身も驚きながら回してるんです。なので、見ている人も自分が激論の渦中にいるかのような感覚になるかと思います」
それぞれが考える正しさが、弱者の存在を窮地に立たす
作品は、ほとんどのシーンがモノクロで進む。これは、あえて色情報を抜き、黒と白のみの極まった世界にすることで、見ている人が自分の心と向き合い自問自答できるようにという思いが込められている。
「ちなみに、女性職員が密室で男性上司に体を触られるシーンも撮影していて、本当は映画のなかに入れていました。ただ、翻訳をお願いしたときに海外の翻訳家からこのシーンは海外だと性暴力やレイプになると言われたんです。日本では“セクハラ”という曖昧な言葉がある故に、こういった問題が放置され続けてきたことを実感した出来事でもあって、あえて入れませんでした。愚かなことに自分も指摘されるまで気付かなかったわけです」

この映画は、明確な答えを出していない。なので、実際に試写に来た人のなかでは、「セクハラを訴えた女性は、職場をかき乱してまで騒ぎすぎではないか」という感想を述べた人がいたり、「どうしてこんなに辛い映画を作るんだ」と言う人がいたり。誰しもがモヤモヤとする終わり方になっている。ただ、エンドロールでは、厚生労働省の統計が流れる。
日本におけるハラスメント件数は年間82797件。約4人に1人がなんらかのハラスメント被害を受けている。そして、その45%は被害後、特になにもせずやり過ごしたーー
「映画でも描いていますが、被害を受けた人は、職場での視線や噂話に耐えなければいけなかったり、ネットで誹謗中傷を受けたり、個人情報が晒し続けられたりします。本当に疲弊すると思うんです。勇気を出して自分の正しさを主張しても、月日が経てば、こことは関係のない世界に行ってしまいたいと思ってしまう。だからこそ、半分近くの人が被害を受けたあとに何もしなくなると思うんですよね」
日本でも、少しずつ勇気を持って声を上げる女性が増えてきた反面、それを仕方のないことだと受け入れない社会や、声を上げた女性を批判するメディア、無法地帯となっているネットでの誹謗中傷など、被害を受けた側が生きづらくなっていく現状は変わらない。どうして、被害者が責められてしまう構造が当たり前とされているのだろう。どうして、諦めてしまわなければならないのだろう。
「日本には長期的に被害者を守るようなシステムがまだありません。海外では、ホイッスルブロワー(組織の不正を密告した人)やハラスメント被害者を、報告がなされたと同時に匿って守らなければいけない、クビにしてはならない、という保護システムが存在しています。第三者が仲介になりコミュニケートも手助けし、弱い個人を<一定期間>組織が保護するのは常識となっているんです。勇気を出して被害を告発したら、逆に会社からも社会からもバッシングを受けてしまう日本では、被害者が耐えられない。問題がヒートアップした一時期でなく、長い時間軸上での被害の見積もりをして対策することが、本当の意味で弱者を守ることなのです」

この映画を見て、これまで自分が経験してきたことと重なる人は少なくないはずだ。作中のキャラクターの誰かと自分を照らし合わせ、やっぱり自分が正しいと思う人もいるかもしれないし、これまでの間違いに気付く人もいるかもしれない。
私たちが今信じている“正しさ”、社会が掲げる“正しさ”は誰のためのものだろう。自分たちが無意識に日々振りかざしている“正しさ”は、ときに弱者の存在を追いやってしまっているのではないだろうか。

『ある職場』
2022年3月5日(土)ポレポレ東中野にてロードショー!
あるホテルチェーンの女性スタッフが上司にハラスメントを受けたという実在の事件を基に、その後日談をフィクション化。事件をうやむやに処理しようとする上層部、噂が噂を呼びざわつく職場、ネットやSNSが誹謗中傷で炎上する二次被害にまで発展。ホテルスタッフの人間関係もあちこち亀裂が入る…。そんな時、ある社員の発案で有志が集まり、湘南にある社員用保養所へバカンスにゆくことに。ギクシャクしている人間関係も改善できればという善意の企画だったのだが…。
男女間格差が先進国中最下位(120位)の日本。「セクハラという罪はない」と宣う政治家までいるジェンダー平等の後進国だ。そんな社会で、ハラスメントの約45%は被害後なにもせず我慢してやり過ごしたと報告されている(厚労省調査)――それは、私たちが未だハラスメントにどう対処してよいのか、本当の意味で理解していないからではないだろうか。本作は、現代日本のあるべきジェンダーバランスの姿を問いかける。
「ポルトの恋人たち 時の記憶」「BIG RIVER」「フタバから遠く離れて」の舩橋淳監督の第9作。

舩橋淳
東京大学卒業後、ニューヨークで映画制作を学ぶ。第1作である『echoes』(2001年)から『BIG RIVER』(2006年)『桜並木の満開の下に』(2013年)などの劇映画、『フタバから遠く離れて 第一部・第二部』(2012,14年)『道頓堀よ、泣かせてくれ! DOCUMENTARY of NMB48』(2016年)などのドキュメンタリーまで幅広く発表している。最新作である『ある職場』は3月5日よりポレポレ東中野にて公開。
▷Twitter

















